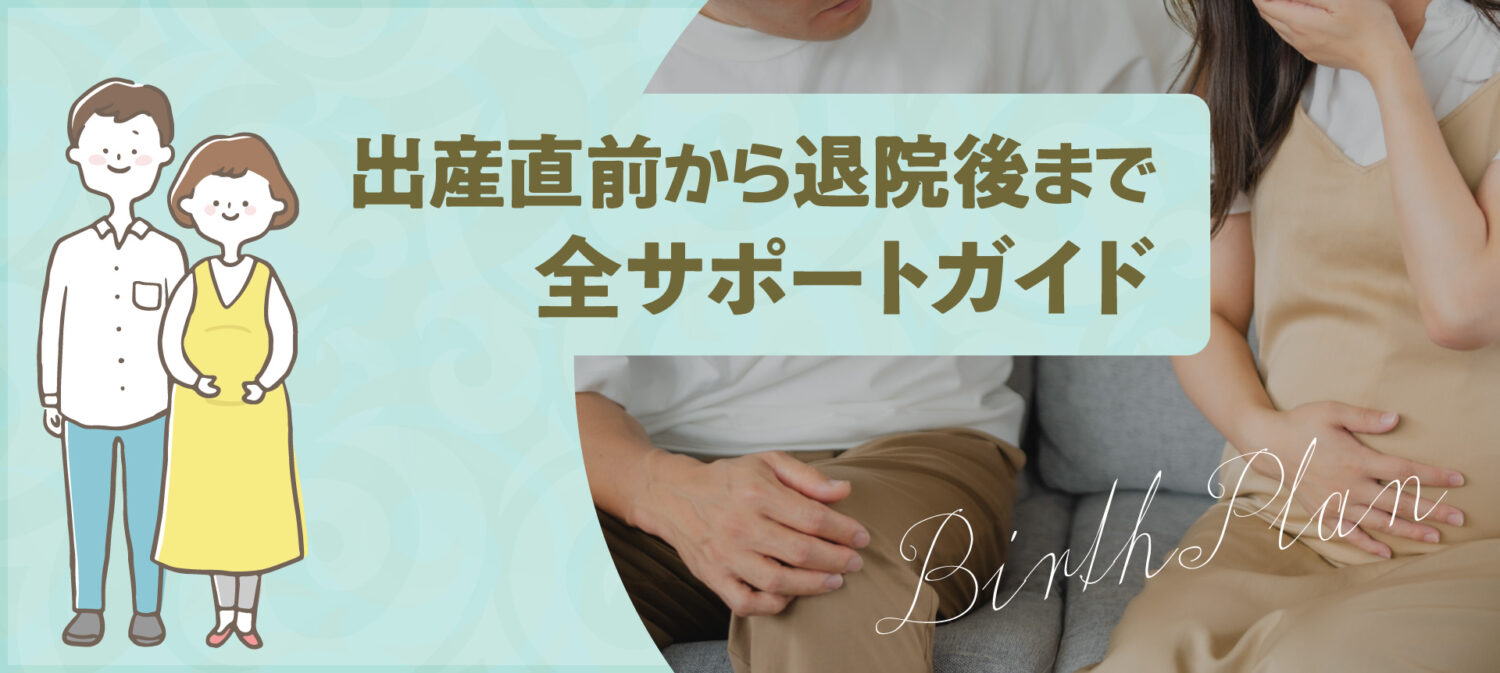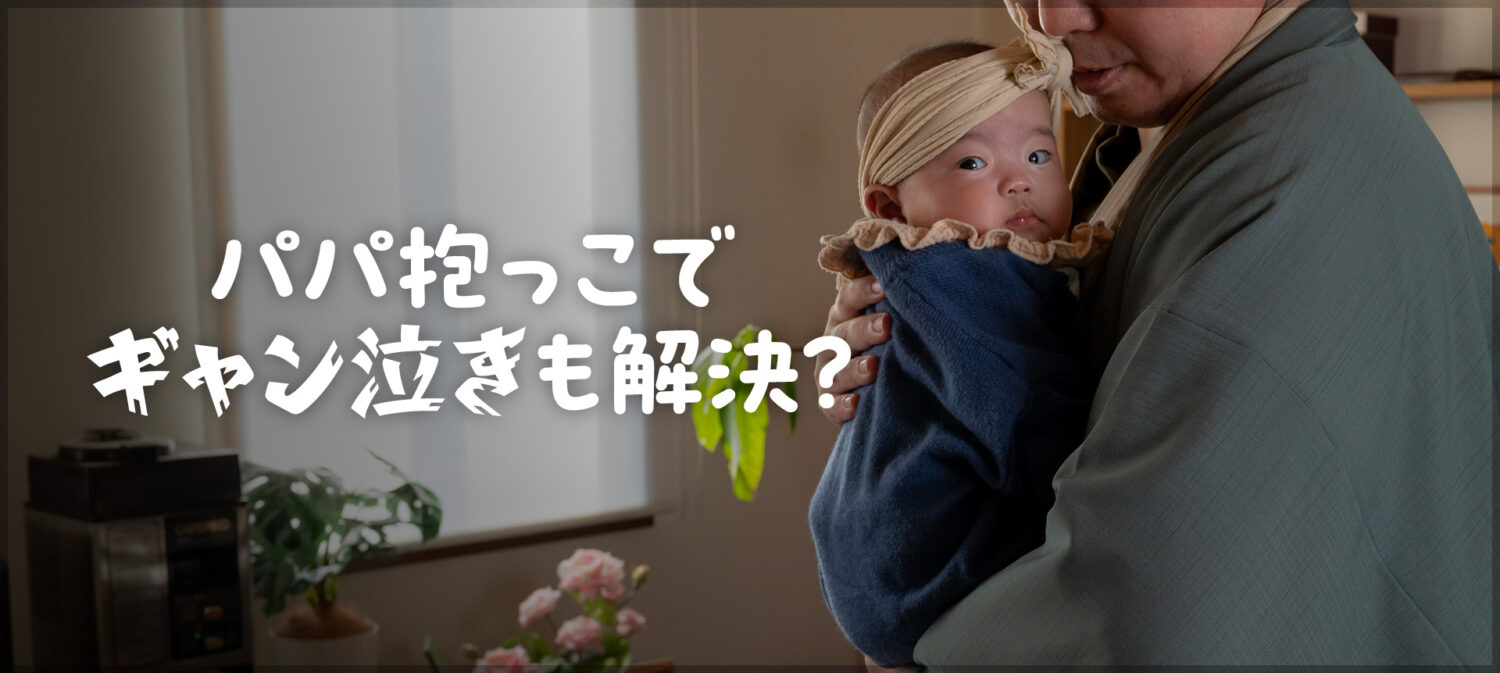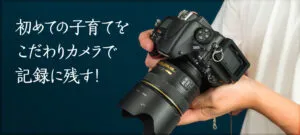出産は、パパにとっても人生の大きな転機です。
初めての経験に不安を感じるかもしれませんが、最初が肝心とはまさに出産・育児でもおなじこと。各段階でパパが積極的にサポートすることは、出産後の家庭円満にも繋がります。
出産前、出産中、そして退院後に向けて、具体的な行動を知っておけば安心です。
この記事は、パパがどのように関わり、育児をサポートできるかを詳しく見ていきますので、是非参考にしてみてください。
目次
出産前(予定日間近)にパパができること
出産日が近づくと、ママもパパもソワソワする時期かもしれません。
陣痛がいつ来てもいいように準備を整え、心の余裕を持って迎えられるようにしましょう。予定日間近のパパがすべき準備をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
出産が近づくと、準備することが本当に増えるよね。
それに、陣痛タクシーの登録も忘れないようにね。突然の陣痛でも対応できるにゃん。
確かに、もしもの事を考えると陣痛タクシーがあると安心だよね。
準備は大事にゃ。しっかり計画しておけば、当日慌てずに済むにゃん。
出産準備品のリスト作成
予定日が近づくほど、出産に向けた最終確認が必要です。
必要なベビーグッズのリストをチェックし、必需品が揃っているか確認しましょう。特に、ベビーベッドやチャイルドシート、新生児用の肌着などは、退院後すぐに使うため、早めに準備しておくことが大切です。
また、ママの入院バッグも準備しておき、忘れ物がないようにしておきましょう。
出産直前に用意するアイテムリスト
絶対に必要なもの
出産前に準備しておくもの
- ママの入院バッグ(着替え、タオル、歯ブラシ)
- パパの立ち会いアイテム(カメラ、軽食、ドリンク)
- 母乳パッド
あったら便利なアイテム
産後のケアアイテム
- 骨盤ベルト
出産前にバースプランを作る
バースプランは、出産時の希望や方針をまとめた計画書で、具体的な出産計画を産院に伝えるためのものです。
パパもこのプラン作りに積極的に参加することで、出産時にどのようなサポートが必要かを理解し、当日スムーズに動けるようになります。
また、産院への連絡手順も共有しておくことで、スムーズな対応ができます。電話番号を事前に登録しておくなど、破水や陣痛がくるまえに用意をしておきましょう。
育児休暇の手配
育児休暇を取得するパパは、できるだけ早めに会社とスケジュールを調整しておくことが大切です。
特に産後の1~2ヶ月は想像しているより大変なものです。育児休暇の期間や具体的なサポート内容を計画しておくことで、家族全体が安心して過ごせる環境を整えましょう。
育児休暇が取れない場合でも、会社に前もって相談し、急な家庭のサポートにも柔軟に対応できるよう、調整を進めておくと良いでしょう。仕事も大事ですが、子供の誕生は一生に一度の特別な出来事です。
上司や同僚とシンプルに相談しておくことで、臨機応変に対応できるケースも多いです。一人で悩まず協力してほしいことを伝えて起きましょう。
陣痛タクシーの登録
出産予定日が近づくと、いつ陣痛が始まるか分かりません。
突然の陣痛に備えて、あらかじめ陣痛タクシーの登録を済ませておくことが大切です。一般のタクシーでは対応が難しい場合もあるため、専用サービスを登録しておくこで安心感が生まれます。県や市が用意している事が多いので確認しておきましょう。
たとえパパが一緒に行く予定であっても、タイミングが合わず送迎ができない場合も考えられます。陣痛が急に来たときの対策として、緊急時の行動をしっかりすり合わせておくと安心です。
カメラの準備を万全に!
最近ではスマホのカメラ性能も飛躍的に向上し、スマホだけでも素敵な写真を撮影できます。しかし、より臨場感や細部まで美しく残したいなら、ミラーレス一眼がおすすめです!
ととと赤ちゃんでは、パパやママにぴったりのカメラ選びについても詳しくご紹介しています。気になる方は、ぜひ関連記事もチェックしてみてください!
こちらもどうですか?
出産立ち会い時にパパができること
出産に立ち会う時、パパはママにとって心強いサポーターです。ここでは、出産時にパパができる具体的なサポートと、立ち回り方を紹介します。
出産立ち会いって、パパができることって意外と多いんだよね。
それに、飲み物を渡すときはストロー付きのボトルがあると便利だにゃん。パパも事前にしっかり準備しておくのが大事にゃ。
そうだね。長丁場になることが多いから、パパも軽食を取ったりして体力を温存するのが大事なんだ。
出産タイミングで必要なアイテムリスト
パパの準備物
- カメラやスマホ
- 軽食や飲み物
ママの入院準備バッグ
- 母子手帳
- 保険証
- その他産院で指定された書類
- 水分補給用のアイテムなど
出産立ち会い中の妻へのサポート
出産の立ち会いは、短時間で終わるものではありません。
例えば、うちの場合で言うと、夜の0時頃に前駆陣痛が始まり、深夜2時には陣痛間隔が狭まって病院へ移動しました。生まれたのは朝8時頃でしたが、比較的スムーズに進んだケースでもこれだけの時間がかかります。
そして、スムーズとは言いましたが……、前駆陣痛から本陣痛に移行するまでの間、そして生まれるまでの長い時間。ママは強い痛みと戦うことになります。
出産は「生む瞬間」が一番痛いと思われがちですが、実際は前駆陣痛や本陣痛の時点から強烈な痛みが続きます。パパはそのことを理解した上で、可能な限りの痛みの緩和に努めることが大切です。
出産中はサポートに徹しよう
陣痛中は深呼吸が大切です。ママに深呼吸を促したり、マッサージをすることでリラックスをサポートしましょう。
また、飲み物を渡す時は、ペットボトルにアタッチメントできるストローなどを用意しておくといいかもしれません。
コミュニケーションがあるだけでも心強く感じてもらえるので、しっかりと支えていきましょう。
バースプランに応じた立ち回り
ママが希望している出産の進行やケア方法を把握し、計画通りにサポートできるよう準備しましょう。たとえば、ママが痛みを和らげる方法を希望している場合、パパはプランに基づいたサポートを行います。
とはいえ、出産は予想外のことが多い場面です。バースプランが予定通りに進まないケースも考えられます。パパは焦らず柔軟に対応できる心構えが必要です。
冷静にプランをフォローしつつ、産院スタッフと協力して状況に応じたサポートを心がけましょう。
パパの体力温存も大切
パパ自身も体力を温存することが重要です。
長丁場になることを考慮し、ママの様子を見ながら、遠慮せずに軽食をとることも必要です。最後までママをサポートするためにも、飲食は出来るタイミングでしてください。
記念撮影は邪魔にならないように
出産中の記念撮影は一生の記念となります。ただし、ママが大変な時にカメラに夢中になるあまり、サポートを忘れたりしないように気をつけましょう!

入院中にパパができること
出産後の数日間、入院中にパパができるサポートは、ママの回復を助け、赤ちゃんとの新しい生活の準備をスムーズに進めるために重要です。
入院中も、パパができることって色々あるよね。
洗濯をしたり、必要な物を買い足したり、面会時間を有効に使うのが大事だにゃん。
あとは手続きや申請の代行もパパがやると、ママが安心して体を休められるよね。
洗濯
入院中、もし病院内にランドリー設備が整っていれば、その場で洗濯ができる場合もありますが、設備がなければ自宅に持ち帰って洗濯をする必要があります。入院予定の産院に、事前確認しておいても良いでしょう。
必要物の補充
入院中、産院では赤ちゃんのおむつやミルクなど、必要な基本的なアイテムは支給されることが多いですが、すべてのものが揃っているわけではありません。
ママが出産後に必要だと感じるアイテムや、産院では提供されないものを買い足すのも立派なサポートです。たとえば、母乳パッドや個別のケアアイテム。ママが欲しいと思ったタイミングで用意してあげましょう。
また、産院で支給されたおむつや沐浴体験を通じた感想をもとに、退院後の生活に備えて必要なアイテムを揃えておくのも大切な準備です。
入院中に必要なアイテムリスト
入院中に揃えるもの
- 哺乳瓶(母乳育児の状況に応じて)
- 沐浴セット
ママへのケアアイテム
- 母乳パット
育児の積極的な関与
新生児のお世話は、パパにとっても育児の経験を深める大切な時間です。首が据わっていない赤ちゃんを抱っこするだけでも、父親としての自覚がついてきます。退院後の準備にもなるので、積極的に関わりましょう。

もしファミリーステイが可能な病院であれば、赤ちゃんのオムツ替えや抱っこを担当すると、ママがしっかりと体を休める時間を確保することにも繋がります。
生まれた瞬間の赤ちゃんとの生活を、楽しんでみてください。
面会時間を有効活用
面会時間が限られている病院の場合、パパが直接サポートできる時間は限られます。
サポートできることは少ないかもしれませんが、その時間は有効活用し、退院までの期間は育児に関する知識を深めるための、学習に時間を使いましょう。
手続きや申請の代行
赤ちゃんが生まれた後には、出生届や健康保険の申請などの手続きが必要です。
この辺りの各種届けはパパが中心になって進めることで、ママは安心して体を休めることができます。ママに頼る事なく進めることができれば、出産後のママにとって非常に大きな助けになります。
退院後にパパができること
退院後はパパが積極的に育児を受け持つ姿勢が求められます。パパが前向きに役割を担うことで、ママの体力回復と家族の健康的なスタートを支えます。
退院後、パパができることって結構たくさんあるよね。夜間のお世話とか、特に大変なんだよ。
ミルク育児なら、パパが夜中にミルクをあげることで、ママが休めるにゃ。
たしかに……!家庭全体がスムーズに回るように心がけるよ。
退院後に必要なアイテムリスト
育児スタイルに合わせて揃えるもの
- 電動搾乳機
- スタイ
検討したいもの
- 抱っこひも
- ベビーカー
夜間のサポート
新生児の赤ちゃんは、胃が非常に小さいため、一度に多くのミルクを飲むことができません。そのため、3時間おきに授乳やミルクをあげる必要があります。
授乳の3時間サイクルは昼夜を問わず続き、特に生まれてから1ヶ月は、夜間の育児が非常に大変な時期です。短い間隔でのお世話が続くため、とてもしんどい期間です。
母乳育児の場合、夜間にパパが直接授乳をサポートするのは難しいかもしれませんが、ミルク育児であれば、パパが積極的に関わることでママの負担を軽減することが可能です。
たとえば、おむつ替えや夜中のミルクはパパが用意し担当することで、ママが少しでも長く休めるようにサポートすることができます。
また、母乳育児の場合でも、パパが積極的に家事を受け持つことで、ママが夜間の疲れを軽減することができます。
育児全体の負担を分散し、家族が一緒に育児を乗り切る体制を整えましょう。
家事や育児の積極的な受け持ち
家事や育児を分担するのではなく、パパが積極的に責任を持って受け持つことが重要です。
赤ちゃんのお世話だけでなく、料理や掃除、洗濯といった家事にも率先して取り組むことで、ママが体力を回復しながら育児に集中できる環境を整えましょう。
また、家事と育児をパパが率先して行うことで、ママの負担が軽減され、家庭全体が安定したリズムで育児を進めることができます。
赤ちゃんとのスキンシップ
パパが赤ちゃんを抱っこしたり、優しく話しかけたりすることで、パパと赤ちゃんのつながりが強まり、パパ自身も育児に対して自信がついてきます。
退院してすぐは、パパとママの育児スキルの差が殆どないと言えます。積極的に育児に関わり、ママに置いて行かれないようにしましょう。

特に、沐浴や抱っこ、おむつ替えは積極的に受け持つと、今後の愛着形成にもプラスに働きます。また混合育児や完ミの場合は、ミルクをあげるのも積極的に受け持つのがオススメです。
パパが早い段階から積極的に育児に関わることで、ママとの育児ギャップを防ぐとができます。
月齢に応じた育児方法を勉強しよう
赤ちゃんの成長に合わせた育児方法を知ることで、パパのサポートももっと楽しくなります!初心者向けの育児ガイドも用意していますので、こちらも読んでみてください。
こちらもどうですか?
パパが家族の支えとなるためにできること
パパが出産前から退院後まで積極的に家族をサポートするためには、各ステップごとに事前の準備が必要です。
必要な物を事前に準備したり、陣痛タクシーの登録、育児休暇の手続き、バースプランの作成といった準備を整えていくことは、出産後の信頼にも繋がってきます。出産当日も余裕を持って対応できるので、是非参考にしてみてください。
育児の準備を通じて、ママと同じ目線に立つことは安心感を高め、育児がスムーズに進む鍵となります。計画的なサポートを行うことで、家族全員が安心して育児に取り組むことができるでしょう。
\この記事をシェアする/