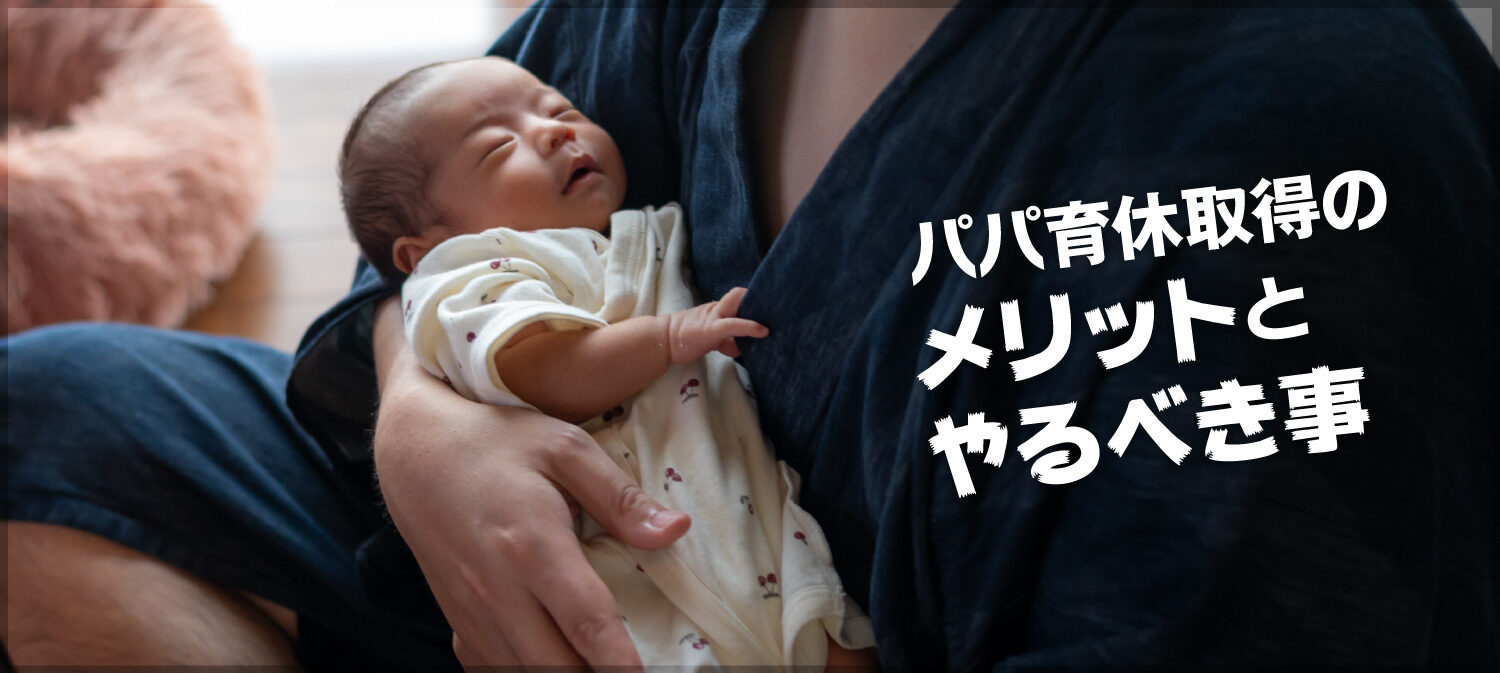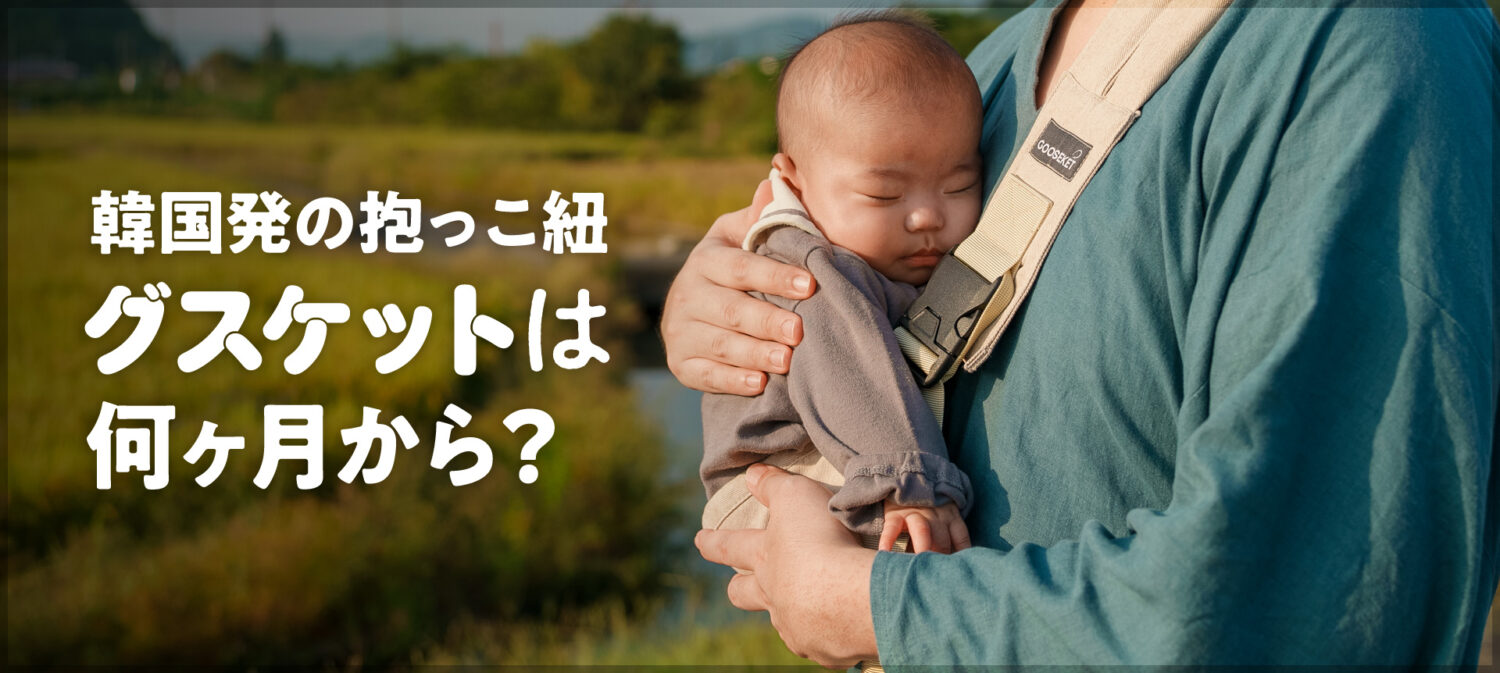近年、男性の育休取得は増加傾向にありますが、依然として取得に躊躇する男性も少なくありません。
日本では長らく育児は女性が中心という意識がありましたが、男性も積極的に育児に参加する時代が到来しています。育休を取得することで、家族との時間を大切にし、育児に積極的に関わることができます。
本記事では、育休を取得することのメリットや、育休中に何をすべきか、また育休期間を有意義に過ごすための具体的なアドバイスを提供します。
目次
男性が育休を取得する5つのメリット
育休を取得することで得られるメリットは、家族、仕事、そして自分自身にとって大きな影響を与えます。ここでは、育休取得の代表的な5つのメリットを具体的に紹介します。
育休を取ると、どんなメリットがあるか一緒に考えてみようか?
真っ先に思い浮かぶのは、子供と過ごす時間が増えることだにゃん。成長を間近で感じられるのは大きいにゃ。
奥さんを助けられるのも重要だにゃん。育児って本当に大変だから二馬力になるとお互いの負担が減るにゃよね。
ちょっと考えただけでもメリット沢山だ!
1. 子供の成長を間近で感じられる
育休を取得することで、赤ちゃんの成長を間近で見守り、新生児期の「はじめての瞬間」を一緒に体験できる貴重な機会が増えます。例えば、赤ちゃんが初めて笑ったり、寝返りをしたりする瞬間を親として共有できるのは、かけがえのない経験です。

また、沐浴などの貴重な体験を自分の手で行うことで、父親としての自覚を高めるだけでなく、赤ちゃんとの絆や信頼関係を強めることにもつながります。こうした経験の積み重ねによって、赤ちゃんの愛着形成がスムーズに進み、パパ見知りのリスクが軽減する可能性があります。
育休中に、赤ちゃんとの関係をじっくりと築くことで、将来的に良好な親子関係の土台を作る絶好のチャンスになります。逆に言うと、この時期を逃すと家族関係がギクシャクするきっかけにもなり得ると言えるのです。
2. 助け合うことで妻の心と体をケア
育休を取得することで、パートナーと家事や育児を協力してシェアし、家庭内での役割をよりバランス良く整えることができます。
育児は体力的にも精神的にも負担が大きく、ひとりで背負うのは非常に大変なことです。しかし、夫婦が互いに協力し合うことで、お互いの信頼が深まり、家庭全体の調和が保たれるでしょう。
特に産後は、パートナーの体調が大きく変化する時期です。出産による身体的なダメージに加え、ホルモンバランスの変化からくる産後うつや、心身の疲労が重なりやすく、感情の波も激しくなることがあります。

重要なのは、男性が積極的に家事や育児に関与し、パートナーを支えることです。
お互いに育児を分担するのではなく、シェアするのが大切です。妻が家事育児をシェアし、夫が受け持つイメージです。男性側が「これくらいで十分だろう」と思う以上に手助けをすることが大切です。
育休中は、家事や育児に対して自ら進んで役割を引き受けることが大切です。主体的な姿勢で家庭に貢献することで、パートナーは安心して自分の時間を持つことができ、心身の回復を促すことができます。家族全員が快適に過ごせる環境を築いていきましょう。
3. 育児を通じて得られる問題解決能力の向上
育児は常に予想外の出来事が起こる連続です。
例えば、赤ちゃんが泣き止まない、予定外に体調を崩す、またはスムーズに進まない日常の小さな問題など、突発的な状況に対応する場面が多々あります。こうした育児の中で求められるのは、瞬時に冷静な判断を下し、適切な対応を取る柔軟な問題解決能力です。
育児を通じてこの能力を高めることで、職場での仕事にも良い影響を与えます。
業務上での突発的な問題や予期せぬトラブルにも、冷静かつ的確に対処できるようになり、よりスムーズに業務を進めることができるようになるかもしれません。育児で培われた「落ち着いて考え、行動する力」は、あらゆる職場環境で強みとなるでしょう。
育児で得られるアンガーマネジメント力
育児では、自分の思い通りにならないことが日常茶飯事です。育児を通じて身につくアンガーマネジメント能力も、職場で大いに役立ちます。
例えば、赤ちゃんがギャン泣きしていて、どんなにあやしても泣き止まない時など、感情に流されそうになる場面が多々あります。しかし、こういった状況でイライラすることは、むしろ逆効果ですし、何より赤ちゃんには通用しません。そのため、冷静に対応し続ける力を養うことが非常に重要です。
育児を通じて鍛えられる忍耐力や感情のコントロールは、職場でのストレスやプレッシャーの下でも冷静に対応できる力として発揮されます。育児中に身につくスキルは、単に家庭内で役立つだけでなく、仕事の場でも非常に有用なスキルとなり、様々なシーンでポジティブな影響をもたらします。
4. 育休を通じた心のリフレッシュ効果
育休は単なる休暇ではありませんが、仕事から一旦離れて家族と向き合うことで、心身をリフレッシュする機会になります。
育児をしている間も、赤ちゃんの笑顔や成長に触れる瞬間は、何にも代えがたい喜びと癒しを与えてくれます。特に子供の純粋な笑顔は、日常のストレスや悩みを吹き飛ばす力を持っており、心の充足感を得ることができます。

リフレッシュした状態で職場に戻ることで、仕事に対するモチベーションが高まり、新しい視点で業務に取り組むことができるようになるでしょう。また、育休中に家族との時間を大切にすることで、家庭と仕事のバランスを見直す機会となり、より効率的な働き方を見つけるきっかけにもなります。
5. 家族全体での協力によって生活の効率が向上する
育休中は、夫婦が協力することで日常のあらゆることがスムーズに進むようになります。
たとえば、赤ちゃんが食事中にぐずったときも、お互いが育児に慣れていれば交代して対応でき、どちらも落ち着いて食事が取れます。パパが育休を通して育児のスキルを身につけることで、夫婦で負担をシェアし、家庭全体がうまく回るようになるのです。

協力体制が自然に定着すると、急な予定変更やトラブルにも柔軟に対応できる力がつきます。誰かが体調を崩したときでも、夫婦で支え合うことで、安心して過ごせる家庭環境が整います。
育休取得のデメリットも知りたい方へ
育休取得にはメリットだけでなく、デメリットもあります。育休取得を迷っている方はこちらの記事も参考にしてください。
こちらもどうですか?
育休中に何をするべきか?
育休は休暇ではなく、家族と向き合い、育児に専念するための貴重な時間です。この期間を充実させるためには、ただ時間を過ごすだけでなく、計画的に取り組むことが大切です。育児や家事を効率的に進め、家族全体が心地よく過ごせる環境を作るための方法を考えてみましょう。
正直に言うと、子供産まれるまでは漠然としすぎて何も思いつかなかったよ。
まずは、家事と育児のバランスを考えることが大切にゃんよ。
育児の知識を深めるのも重要だにゃん。無知のままじゃできることが限られるかにゃん。
1. 家事と育児の役割に固執せず、臨機応変に対応する
家事や育児の分担を明確にするのではなく、役割に固執しすぎずに柔軟に対応できることが重要です。
たとえば、朝の掃除や夕食の準備、洗濯といった日常の家事は、どちらか一方が担当すると決めても、ギャン泣き対応で手が回らないなんて事もあるでしょう。そんな時に、パートナーが自然に手助けできる関係が築ければ、負担は大幅に軽減されます。
育児に関しても、授乳やおむつ替え、夜泣き対応など、臨機応変に気がついた人が行うことを基本にし、状況に応じて柔軟に対応することが求められます。

お互いができる範囲で協力し合うことで、ストレスを減らし、家庭全体のリズムが整いやすくなります。大切なのは、「家族みんなで助け合う」という姿勢を持ち、計画が崩れてもお互いをサポートし合える柔軟さです。これにより、育児や家事がスムーズに進むだけでなく、夫婦の信頼感も深まります。
2. 育児に積極的に参加し、知識を深める
育休中は、育児に積極的に参加することで、自然と「もっと知りたい」という気持ちが芽生えてくるものです。
赤ちゃんの発達段階や、栄養、睡眠に関するさまざまな疑問が湧いてきたら、それをきっかけに学んでいくことで、育児に対する安心感も増していきます。育児書や信頼できるウェブサイトを活用しながら、赤ちゃんの成長に合った対応を先回りして準備しておくのもおすすめです。
また、地域の育児支援サービスや保育園の一時預かりなど、外部サポートについても育休中に調べておくと、いざという時に安心して利用できるでしょう。疑問が出たらすぐに調べて解決する習慣をつけることで、急な育児の困りごとにも柔軟に対応でき、育児に対する自信もついてきます。
3. 家族との時間を大切にしながら、スキルアップを図る
育休中は赤ちゃんとの時間はもちろん、パートナーとの時間も大切にしたいものです。育児に追われていると、夫婦で過ごす時間が減りがちですが、赤ちゃんが寝ている間やお世話の合間に、夫婦でリラックスできる時間を設けるよう心がけましょう。
育児の負担が大きくなると、どうしてもストレスがたまりがちです。たとえば、交代でワンオペ対応をする日を設けることで、どちらかが1日リフレッシュできる時間を確保し、心身のケアを行うことができます。
妻に余裕ができたときは、今度はパパのための勉強時間を確保するなど、お互いに支え合いながら成長していける環境を整えましょう。
時間の使い方や協力のしかたを工夫することで、家族全体の絆が深まり、育児や家庭の負担を軽減しながら、自分のキャリアや成長にも時間を使うことができるようになります。夫婦で互いに支え合いながら、家族としても個人としても充実した時間を過ごしていきましょう。
結果として、家族全体が心地よく過ごせる環境が整っていき、育児が楽しいと思える時間が増えていくでしょう。
具体的な育児の紹介
育休中にパパが取り組むべき育児の中で、特に赤ちゃんとの絆を深めるためにおすすめの作業を紹介します。初めての育児でも安心して取り組めるように、具体的な方法をステップごとに説明します。
実際に体験してみた具体的な内容を書いてみたよ!
1. 沐浴(お風呂の時間)
お風呂の時間は、パパが赤ちゃんとスキンシップを取る絶好の機会です。
特に母乳育児の場合、ママは授乳を通じて赤ちゃんと頻繁に接しますが、パパはその機会が限られます。そのため、沐浴はパパが担当するのに最適です。肌と肌が触れ合うことで、赤ちゃんとの絆が深まり、安心感を与えることができます。
沐浴のポイント
- お湯の温度を37〜38度に設定し、ガーゼやバスタオル、着替えを用意しておきましょう。
- 頭と首を片手でしっかり支えて、ゆっくりとお湯に浸けてあげます。この時耳にお湯がはいることはないので、耳を塞ぐ必要はありません。
- シャンプーをしてあげたら、おでことほっぺにちょこんと泡をつけてあげ、顔を洗ってあげましょう。その後、特に首のシワや関節の部分など、汗がたまりやすい箇所を丁寧に。
- 体が冷えないようにすぐにタオルで包んで、しっかり拭きましょう。

お風呂の時間は、パパが自分の役割を持ちながら赤ちゃんとスキンシップを図れる大切なひとときです。
2.服の着せ替え
赤ちゃんの服の着せ替えも、日々の育児に欠かせない作業です。着せ替えの時間は、赤ちゃんとのコミュニケーションを深める良い機会でもあります。パパが着替えを担当することで、赤ちゃんとの触れ合いの時間が増え、絆を強めることができます。

さらに、沐浴と着せ替えをセットでできるようになっておくことはとてもオススメです。
どちらも毎日行う作業であり、この2つができれば、いざという時にママに依存せずに対応できるため、パパとしても自信を持って育児に臨むことができます。特に、ママが休んでいる間や外出時など、パパが一人で赤ちゃんのお世話をする場面でも安心です。
3. オムツ替え
オムツ替えは育児の基本であり、日々何度も行う作業です。
パパも積極的に参加することで、赤ちゃんとのコミュニケーションを深められます。特に、慣れてくると短時間でスムーズに行えるようになるため、育児の負担感を軽減することができます。
オムツを交換したときに声がけも忘れずおこないましょう。しっかりコミュニケーションを取ることで3ヶ月期頃には笑顔も見られるようになります。めちゃくちゃ可愛いのでオススメですよ!
オムツ替えの手順
- 新しいオムツを用意します。うんちの場合はお尻ふきを数枚用意しておくと便利です。
- 赤ちゃんの足裏を重ねるようにして優しく持ち上げながら、汚れたオムツを取り外します。
- 前から後ろに向かって、おしり拭きでしっかりと清潔にします。おしっこの場合は賛否あるみたいですが必ずしも拭かなくてもいいみたいです。
- 新しいオムツを装着します。指がはいるぐらい少しゆとりがあるのがベストです。
パパもオムツ替えを積極的に担当することで、育児に対する自信を持ち、赤ちゃんとの日常的な接触を増やすことができます。
4. ミルクをあげる(混合育児・完全ミルクの場合)
母乳育児が中心の家庭でも、混合育児や完全ミルク育児の場合は、パパもミルクをあげることができます。授乳は赤ちゃんと親との重要なスキンシップの機会であり、ミルク育児の場合、パパもこの役割を担うことで、赤ちゃんとの絆を深めることができます。

粉ミルクをあげる際のポイント
- 粉ミルクを作る際は一度沸騰させたお湯を使用し、80度以上の温度で溶かします。粉ミルクに含まれる細菌をしっかりと除去するためです。
- ミルクを適温に冷まします。うちではボウルみ水を張って、その中に哺乳瓶を入れて冷ましています。人肌くらいの温度に調整しましょう。
- 赤ちゃんを抱っこして、しっかりと抱きかかえた状態で授乳しましょう。目を合わせながら、赤ちゃんのペースで飲ませてあげるのがポイントです。
- 授乳後は、赤ちゃんの姿勢をまっすぐにしてゲップを促します。背中を叩く必要はありません。
ミルクをあげる時間は、赤ちゃんとじっくり向き合い、親子の絆を深める大切な時間になります。
5. 赤ちゃんをあやす
赤ちゃんが泣いたりぐずったりした時、抱っこやおもちゃであやすことは、パパができる最も身近な育児作業の一つです。赤ちゃんが安心できる姿勢や環境を作ってあげることで、泣き止んだり、リラックスさせることができます。

パパが積極的に赤ちゃんをあやす時間を持つことで、赤ちゃんとの信頼関係をより深め、日々の育児が楽しく感じられるようになるでしょう。
6. 寝かしつけ
寝かしつけは育児の中でも大きな役割の一つです。特に赤ちゃんは眠りが浅く、夜中に何度も目を覚ますことがあるため、寝かしつけをうまく行うことが重要です。パパが寝かしつけを担当することで、赤ちゃんとの絆を深めると同時に、ママの負担も軽減できます。

寝かしつけを習慣化することで、赤ちゃんはより安定した睡眠を取ることができ、パパとの絆も深まります。パパが積極的に寝かしつけを担当することで、ママの夜間の負担も軽減され、家族全体の生活リズムが整いやすくなります。
まとめ
育休を取得することは、家族と向き合い、育児に積極的に参加するための非常に貴重な機会です。
男性が育休を取得するメリットは、家族との絆を深めることはもちろん、仕事に対する新たな視点や、パートナーとの協力体制の確立にもつながります。また、育児を通じて得られる柔軟な問題解決能力や忍耐力は、職場でも大いに役立つでしょう。
育休中は、家事や育児を通じて家庭の基盤を整えるだけでなく、心のリフレッシュや自己成長の機会としても活用できます。家族全体が協力し合い、パパも積極的に育児や家事に関わることで、家庭全体がスムーズに回り始め、育児が楽しいと思える時間が増えていきます。
パパが育児に参加することは、家族にとっての大きな財産となり、育休を通して築いた絆や経験は、今後の家庭生活にも大きな影響を与えるでしょう。これから育休を取得しようと考えている男性の方々が、安心して一歩を踏み出し、充実した育休生活を送れることを願っています。
\この記事をシェアする/