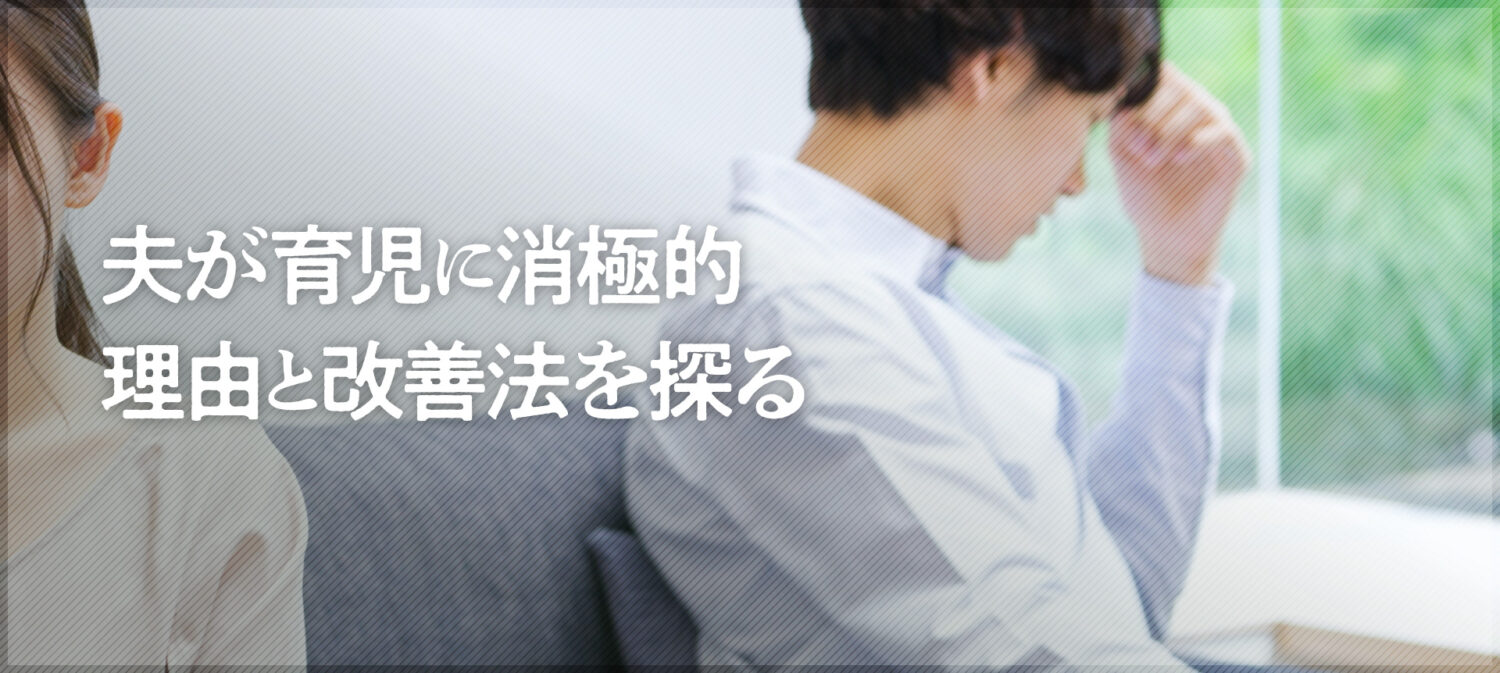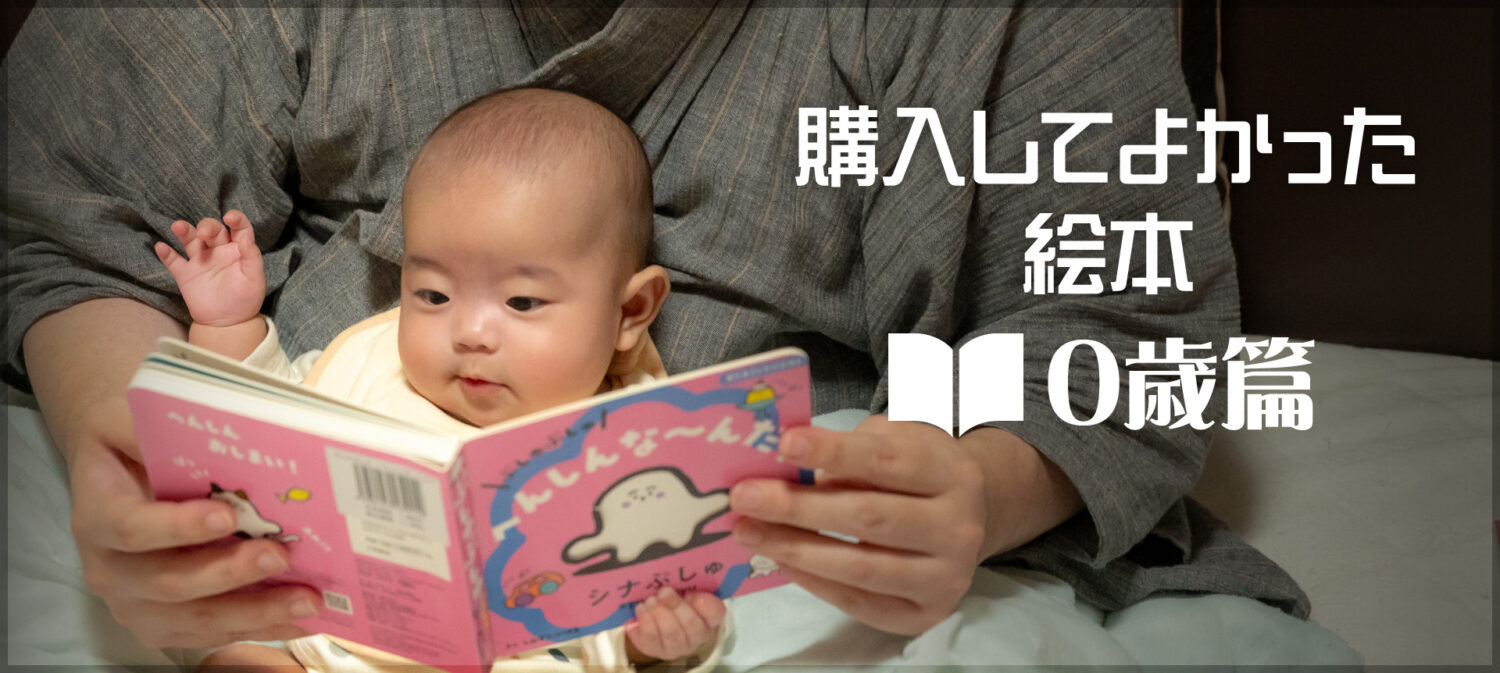夫が育児に関心を持たず、調べようともしないことで悩む妻は少なくありません。自分の子どもなのに、なぜ父親が育児を他人事のように感じてしまうのか、不安や戸惑いを覚える場面も多いでしょう。
仕事の忙しさや、自分には育児が向いていないという思い込み、さらには育児は妻が担うものだという根強い価値観が、夫を育児から遠ざけていることが考えられます。
では、どうすれば夫が育児を他人事ではなく自分のこととして意識し、自然に関わってくれるようになるのでしょうか。
この記事では、その背景に隠れた本音に触れつつ、具体的なアプローチを探っていきます。
目次
夫が育児に消極的になる背景とその本音
夫が育児に消極的な理由には、仕事や職場環境の負担に加え、家庭内での役割意識や育児に対する苦手意識など、さまざまな背景が絡み合っています。妻が気づかないうちに、育児から距離を置いてしまうケースが少なくありません。
正直、仕事が忙しい人の気持ちもわかるなぁって思う時あるよ。
うん、やっぱり毎日働いて、さらに育児ってなると負担も大きいよね。だから、育休があるのは本当にありがたい。
それぞれの事情があるから、無理しすぎずできる範囲で関わるのが大事にゃね。
忙しい仕事による心身の負担とストレス
現代の男性は、長時間労働や残業が日常化しており、心身ともに疲れ切った状態で帰宅することが多いと言えます。
家に戻っても気力が湧かず、育児や家事に十分に参加する余裕がないと感じがちです。たとえ内心では育児に関わりたいと思っていても、仕事の負担やストレスがそれを阻んでしまう現状があります。
- 仕事と育児の両立が困難
- 帰宅後の体力不足
- 家庭を維持するためのプレッシャーでストレス過多
- 理解されづらいがリフレッシュしたい
本音では家族のために育児に関わりたいと願っている男性も多いのですが、仕事の重圧が育児から距離を置く原因となり、結果的に妻とのすれ違いや理解不足を招くことにもつながっています。
家事や育児に対する苦手意識
育児や家事は、経験が少ないと「自分には向いていない」と感じやすいものです。
これは残念なことではありますが、日本では家事や育児が苦手という男の人が多く、どこから始めていいか分からずに尻込みしてしまうことが多い状況です。また、周囲やメディアで見かける理想の育児のイメージに対して、完璧にできなければ意味がないと考えてしまう傾向もあります。
- 苦手意識が育児や家事から逃げる口実に
- 完璧主義やプライドの高さから尻込み
- やろうとすれば出来るのに、最初の一歩を避ける
少しでも失敗することを恐れるあまり、実際には何もできない状況に陥ることもあります。苦手意識やプライドの高さが距離を置いてしまう要因となり、育児に積極的に参加できない現状を生んでいます。
手っ取り早く、育児書を読んでみるのもオススメです。
育休取得の後ろめたさと難しさ
男性の育児休暇取得が社会的に進んでいるとはいえ、現場ではまだまだ実現が難しいのが現実です。

特に日本では、育休を仕事を休む行為と捉える風潮が強く、同僚や上司に育児休暇を取りたいと申し出ることに対して心理的なハードルが高い傾向があります。職場での理解が得られず、育休の取得に後ろめたさを感じてしまう男性も多いです。
- 職場の理解不足
- キャリアへの影響を不安視
育児をとりたいと本音では思っていても、職場での制約や周囲の目線がそれを難しくしているのが現状です。キャリアに悪影響が及ぶのではないかと懸念することも、育休を遠ざける要因となっています。
ただし、職場に理解をもとめる事とキャリアアップを狙うことは同時進行できることです。片方を捨てるのではなく、両方を両立できるように摺り合わせていく力をつけましょう。
育児は「妻の仕事」という意識の根強さ
昔から、家事や育児は妻が主に担当するという価値観が多くの家庭で根付いています。多くの世帯で共働きが見られる令和ですら、未だにその意識は改善されていません。
夫は、無意識のうちに育児は妻が主に担うべきと考えがちであり、どうしても育児への関わりを後回しにしてしまいます。また手伝うという立場で関わることで、主体的な育児参加が妨げられてしまう場合もあります。
育児は手伝うものではなく、自分の責任として自覚することが大切です。
夫の意識が変わらない限り、夫が育児に主体的に関わるのは難しいかもしれません。ですが、改善しなければ家庭崩壊の危機にもなりかねません。価値観を見直し、育児に対して責任をもちましょう。
夫が育児に積極的に関わるためのポイント
父親としての役割をしっかりと理解し、逃げずに子どもと真剣に向き合うことが大切です。親としての責務を果たすためにも、父親が積極的に育児に関わるための具体的なポイントを見ていきます。
子どもが生まれたとき、真剣に向き合わないとダメだなって実感したんだ。
赤ちゃんは親のサポートが必要不可欠だにゃん。だからこそ、パパもちゃんと向き合うのが大事だにゃ。
今までは仕事優先だったけど、子どもと一緒にいる時間がどれだけ大切かって実感したよ。
子どもに関わることの大切さを再認識する
子どもを育てるのは親として至極当然の役割です。それなのに、育児を妻に任せてしまっても大丈夫と思っている現状は、何かが間違っている状況と言えます。
もちろん、仕事が忙しかったり、ストレスが溜まったりするのは事実であり、家族にも理解してもらうべき部分でしょう。しかし、育児には待ったなしで対応が求められます。だからこそ、状況が大変であればあるほど、親として自覚を持ち、必要に応じてサポートを求めることが大切です。
例えば、上司や同僚に相談してみることで職場の協力が得られることもあります。また、必要であれば自治体のサポートを活用し、県や市に相談することも一つの手です。育児に真剣に向き合う姿勢が、家庭全体の幸福や子どもの健やかな成長を支える基盤となります。
妻の負担を理解し、分担ではなく受け持つ姿勢を持つ
妻がどれほど大変な思いで日々を過ごしているか、実際に体感することが重要です。
育児や家事は単に手伝うのではなく、夫婦ともに主体的に動きながらもシェアする気持ちが大切です。妻がこれまで一人で担ってきた負担を少しずつ受け持ってみましょう。

その際、妻側も夫に厳しい物言いを避け、気持ちよく協力し合える環境づくりを心がけることが大切です。ただし、夫は頼まれたことに嫌な顔をせず、率先して行動する姿勢を持つと、家庭の円満さにつながります。
完璧を目指す必要はありません。夫婦で協力しつつ、無理なくできる範囲で前向きに取り組むことが、家庭の円満な成長につながります。
具体的に意識したいポイント
- 妻がこれまでにしてきた育児や家事を具体的に把握する
- 育児・家事はお互いが主体的になりながらシェアするものだと意識する
- 夫が率先して受け持つ姿勢を持つ
- 妻に頼まれたことに嫌な顔をせず、すぐに対応する
- 完璧主義を捨て、できる範囲で取り組む
- お互いに気持ちよく協力できる環境を作る
- 夫は積極的に職場や自治体のサポートを活用する
小さなことから変えていく
育児に参加することは、決して完璧を目指す必要はなく、小さなことから関わりを増やしていくことで成り立ちます。
例えば、妊娠中から少しずつ家事を引き受けたり、出産後は簡単なおむつ替えや沐浴を担当するなど、身近なことから始めると効果的です。すでに子どもがいる場合でも、日常的に関わることで徐々に自信がついていきます。
少しずつ「できること」を増やす
朝の支度やお風呂など、無理なく取り組める家事や育児から始め、徐々に関わりを増やしていくことで育児への自信がつきます。小さな成功体験が大きな関わりへと繋がる
小さなことでも「できた」と感じる体験が、父親の自信を育み、家庭での役割を果たしていくモチベーションにつながります。
職場や同僚に家族第一であることを伝える
父親が家庭に関わる姿勢を持ちやすくするには、職場や同僚の理解が欠かせません。
職場で家族第一の姿勢を示し、早めに帰れる日は帰宅するなど、家族と向き合う時間を確保するための行動を心がけましょう。周囲に協力を求めることで、家庭とのバランスも取りやすくなります。
家族の優先を職場で共有する
職場で家族第一の考えを伝え、育児参加への協力を周囲に求めることで、家庭と仕事の両立がしやすくなります。周囲の理解を得るための行動が鍵
家族を大切にする姿勢が職場に浸透することで、父親としての役割も果たしやすくなり、家庭を支える力に繋がります。
父親が育児に積極的に関わることで、子どもの成長や未来に直接寄り添う責任を果たし、家族の絆も一層深まります。日々の小さな行動から、家庭全体の安定と幸福を高めていきましょう。
今日から始められる育児への効果的な関わり方
子どもが生まれたとき、夫婦は同じスタートラインで育児の知識を持ち、共に学びながら成長していくものです。
ただ、育児に関わる機会が少なかったことで、育児において妻との差ができてしまった場合、まずは妻がどのようなことを日々行っているかを知ることが、育児に関心を持つための第一歩です。
ママが特別に育児に詳しいわけじゃないって前提も大事だよね。
だからこそ、一緒に学んでいく姿勢が大切なんだ。わからないことがあってもお互いサポートしながらやっていくって感じで。
二人で成長していけば、赤ちゃんも安心してすくすく育つにゃん!
育児について学ぶ姿勢を持つ
育児の基本を知ることは、自信を持って関わるための土台です。仕事と同じように、まず基礎を押さえることが大切です。育児書やネット記事(たとえば当サイト)を参考にして、少しずつ知識を増やしていきましょう。
基礎知識を身につければ、妻が日々行っている育児の大変さも理解でき、自分がどのように関わるべきかが見えてきます。
育児は一人で担うには大変ですが、夫婦で協力することで育児や家事の負担が大きく軽減されます。役割をシェアし、効率よく進める工夫ができれば、仕事上のストレスも自然と軽くなり、赤ちゃんの笑顔に癒される瞬間が増えるかもしれません。
関連記事として、出産前、主産後のパパ向けガイドもまとめてあります。ぜひ参考にしてみてください。
こちらもどうですか?
実践的なポイント
妻が日々行っている育児を把握する
まずは妻の育児や家事の内容を具体的に理解し、負担を知ることがスタートです。育児の基本を押さえ、応用する
育児書や育児記事を読んで基礎を身につけることで、自分がどう関わるべきかが見えてきます。夫婦で負担をシェアする
どちらかが一人で抱え込まず、二人で協力することで効率的に進められるように話し合います。育児の楽しさを見出す
基礎知識を実践し、子どもと過ごす時間に喜びを感じられるように意識してみましょう。
まずは頭ごなしに出来ないと決めつけるのではなく、夫婦で協力し合い、お互いの意見を尊重することが大切です。夫は協力する姿勢を前面に出し、妻をがっかりさせないよう努めましょう。
育児は完璧を目指す必要はありません。少しずつ夫の努力を認めながら、二人三脚で育児に取り組んでいきましょう。
育児は二人三脚で、家族みんなが幸せに
夫が育児に関わるのは特別なことではなく、親として当然の役割です。
子どもの成長を見守りながら、一緒に日々を過ごしていくことは、父親も母親も担うべき大切な責任。ただ、育児に完璧さを求めすぎる必要はありません。むしろ、肩の力を抜いて「できることから始める」くらいの気楽な気持ちでいるほうが、家庭全体に余裕が生まれます。
小さな成功体験を重ねながら、少しずつ役割を増やし、無理のないペースで関わっていくことが大切です。お互いの立場を尊重しつつ、協力し合う姿勢が自然と当たり前になれば、家族みんなが安心して笑顔で過ごせる家庭が築かれていくでしょう。
肩の荷を降ろしながら、今日からできることを一歩ずつ。家族の温かさと安定を支える日常を、一緒に育んでいきましょう。諦めない心が何より大切です。
この記事を書くにあたり、以下の文献を参考にしました。
参考文献:J-STAGE 日本家政学会誌(夫は妻の育児感情をどう認識しているか (第1報) 妻の育児感情と夫の認識とのずれについて)
\この記事をシェアする/