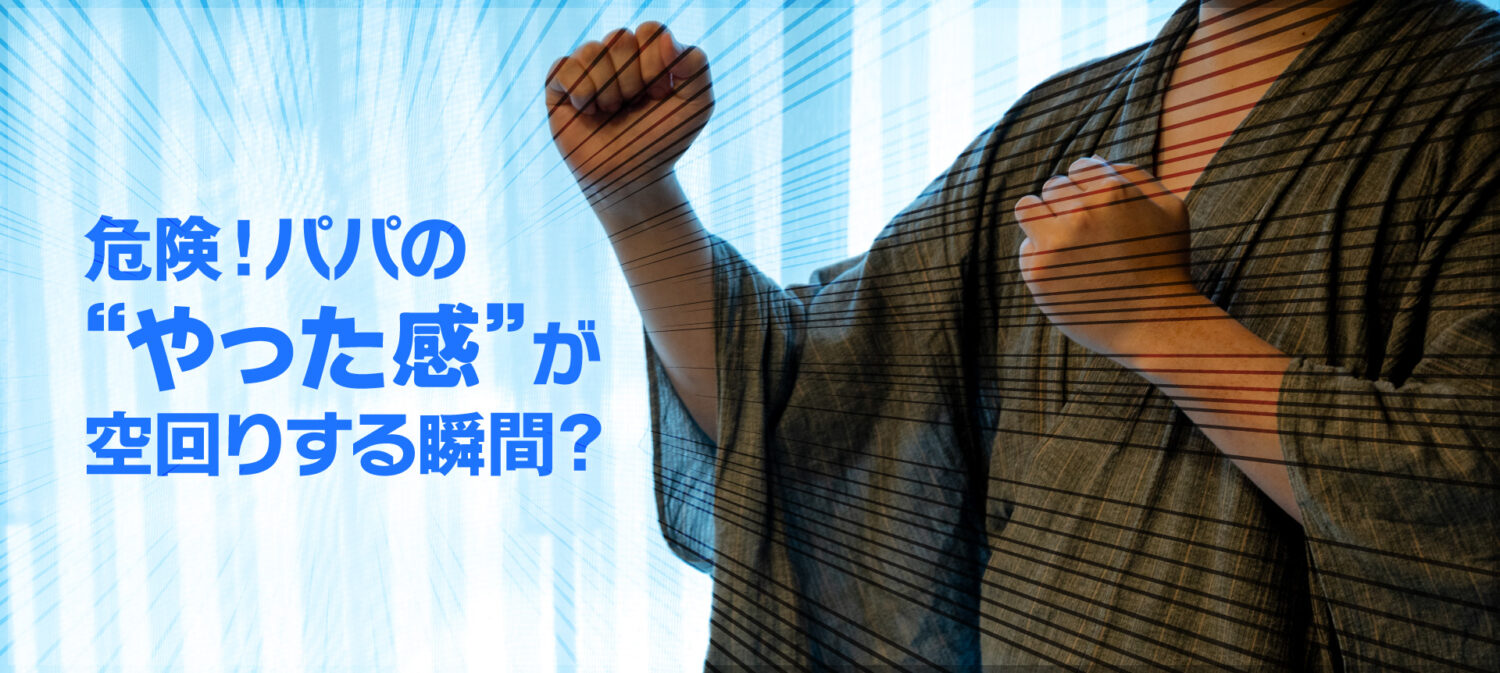育児は、パパとママが一緒に育むことですが、実際は知らず知らずのうちに温度差が産まれていることがよくあります。パパが一生懸命やっているつもりでも、ママは24時間体制で赤ちゃんを守る緊張感の中にいるため、パパとのギャップが生まれ、心労が蓄積してしまうのです。
その結果、イライラしてしまうママさんも……。
この記事では、パパが一生懸命やっているのに、それがなぜ空回りしてしまうのか、その原因を一緒に考えていきます。そして、パパがどうすればママの負担を軽くし、二人でより良い育児パートナーシップを築けるのかについて、具体的なヒントを紹介します。
目次
パパの「やってるつもり」が空回りする理由
まず大前提として、赤ちゃんは非常に不安定で繊細な存在であるということです。
赤ちゃんは常にサポートを必要とし、その小さな体はまだ自分で安全を守ることができません。そのため、ママの心労の原因は、赤ちゃんが一瞬でも目を離せば危険にさらされるという不安感からきています。
最初は自分はやってるんだぜ!!って気持ちで、家事も育児もバッチリ手伝ってる!って思ってたよ。
それは良くないニャン!!手伝ってるって感覚だと、他人事にゃんよ。
そうなんだよね……。今から考えると反省だよ。
コミュニケーション不足がもたらす育児ストレス
パパとママの間で生じる不和の原因は、一言で意識の違いによる温度差が大きいです。
赤ちゃんが産まれたとき、ママとパパのスタートラインはほぼ同じ。しかし、ママは赤ちゃんを守るためにどんどん成長していきます。それに対して、パパは積極的に育児に参加しないと置いて行かれてしまいます。
この違いが、パパとママの間に温度差を生み、コミュニケーションのギャップを生む原因となるのです。この温度差は蓄積され、些細なことにもイライラする原因になります。
パパは何をすべきかを考えながら、赤ちゃんやママと積極的にコミュニケーションを取る姿勢が求められています。
パパの育児参加時間が少ないことによる影響
育児に参加する時間が短いと、育児の大変さを目にする機会が減り、パートナーへの負担の大きさを実感することが難しくなります。つまり、育児がそれほど大変ではないという誤解が生じ、片手間で対応できると考えてしまいがちです。
誤解はさらに蓄積されていき、パパは自分の育児の取り組みが十分だと過大に評価する傾向が強まります。この自己評価の高さが、結果としてママとの間に認識のギャップを広げてしまうのです。
育休取得が少ないことによるデメリット
パパが育児休業を取得しない、または取得期間があまりにも短いと、ママとパパの間に温度差や認識のギャップが広がりやすくなります。仕事をしながら育児をすることは可能ですが、育児休業の取得は非常に重要と言えるでしょう。
育児休業を取得し、育児にじっくり取り組むことで、より効果的に育児参加ができるようになります。世間では育休取得がしやすい流れになりつつあるので、可能な限り育休を取得するようにしましょう。
自分時間があるのに、育児時間は短い
パパは自分の時間を持てる一方で、ママにはその余裕がなく、結果として育児にかける時間のバランスが崩れてしまうことがよくあります。
これは単純に、仕事によるストレスを発散させる必要があるだけですから、一概に悪いとは言えません。しかし、ゲームに夢中になりすぎてしまったり、ちょっとしたお願いを断る口実にしてしまったりすると、ママの不満が蓄積されてしまうことがあります。
こうした行動が積み重なると、ママの負担は増え、結果として育児に対する温度差が広がる原因になることが多いのです。

ママのストレスを減らすためにパパができること
最初は、家事や育児を半分ずつ分担しようって考えてたんだ。でも、実際には仕事中は妻に任せることが多くて、うまくいかなかったんだよね。
育児って24時間体制だから、それだとママの負担が増えてしまいそうだにゃんね。
うん。役割分担にこだわってたけど、結果的に妻が多くやってる状態になっちゃうからね。
具体的なコミュニケーションをとる
日々の育児の中で、お互いの気持ちを具体的に話し合うことが大切です。できる限り早い段階、可能であれば妊娠中から育児の協力体制を築いておくと、よりスムーズに育児を進めることができます。
育児中の不満や要望、沢山あると思います。
パパは気がききづらく、それにイライラすることもあるかもしれません。ただ、それを責めるのではなく、ママがどの部分で助けが必要なのかを率直に伝えることが大切です。はっきり伝えることで、パパもはっきりと認識できます。
パパは伝えられたことはできるだけ早く実行することが大切です。頼まれ上手になれば、ママはどんなことであっても頼みやすくなり、お互いのコミュニケーションも円滑になります。
ただ、もし面倒くさがったり嫌な顔をしてしまうと、それが2回3回と積み重なると信頼を失うきっかけにもなります。お互いの気持ちを尊重しながら、協力して温かい家庭を築いていきましょう。
役割分担にこだわらず柔軟に対応する
役割分担を決めてしまうと、うまくいかなかったときに不満が生まれやすくなります。特に日中パパが仕事で不在の場合、家事・育児分担することで逆にママの負担が非常に大きくなり、過酷さを感じやすくなる原因になる危険性があります。

役割分担にこだわらず、お互いに出来ることを出来るタイミングでやるスタイルが大切です。パパは特に積極的に自分ができることを探し、素直に受け入れて行動する姿勢を持つことで、ママの負担を軽減してあげましょう。
小さな成功を共有する
イライラしていると、「やって当たり前」という気持ちが強くなり、ちょっとしたことにも腹立たしさを感じることがあるかもしれません。ですが、パパの育児参加を認めて、感謝の気持ちを伝えることは大切です。
もちろん、パパ自身も、ママに感謝の気持ちを伝えることが大切です。お互いに励まし合える環境があることで、家庭の雰囲気は自然と温かくなります。

小さな言葉が、相手のモチベーションを高めるきっかけになります。日々感謝の気持ちを持ち、育児を通して信頼関係を深めていくことが重要です。
パパがワンオペ育児を取り入れて、ママをリフレッシュ!
パパがワンオペ育児をこなせるようになると、ママにとって「この人に任せても安心だ」という気持ちが芽生え心にゆとりが生まれます。私自身の経験から言えば、ワンオペ育児は一度だけならそれほど難しいものではなく、むしろやりがいを感じるものです。
しかし、それが毎日続くと話は別で、継続的な負担が非常に大きくなります。
つまり、連続して続けることの難しさを理解できると、パートナーへの理解も深まり、信頼関係がより強固になります。パパが大変さに共感できる土台が必要です。

パパが主体的に取り組むべき具体的な行動
自分がやったことに対して、手伝ったんだから認めてほしい!って思ってたんだよね。
にゃんかわかる気がするにゃ。やったら当然感謝されると思っちゃうにゃん。
そうそう、だから最近は考えを改めたよ。
ママの声をしっかりと聞くことを最優先にしましょう。
もし自分が誰かに頼み事をしたとき、嫌な顔をされたり間が空いてしまうと、頼むのもめんどくさくなったりしませんか?そして、そうした小さな積み重ねは本当にしんどいものです。
ママが気持ちよくお願いできるように癖をつけましょう。これは子供が大きくなったときにも必ずメリットになると感じています。嫌なお父さんになるのではなく、お父さんなら叶えてくれる!という流れを自分から作って行きましょう。
育児について学ぶ
育児は経験を通じて学ぶことが多いですが、あらかじめ知識を持っておくと安心感が増します。
パパがママの知らなかったことを活かして育児を手伝ってくれると、ママはとても嬉しく感じるものです。それは、パパが同じ目線で育児に関わってくれていると感じられるからで、心強いサポートになるからです。
小さなところでは、おもちゃを選んだり、読み聞かせをする絵本を買ってきたり。そんな小さなことが始まりでもいいと思います。小さな積み重ねによってお互いの理解が深まり、協力する体制がより強固になれば、家族全体の幸せが増し、より良い育児環境を作ることができるでしょう。
自主的な行動に対価を求めない
時間に余裕があるとき、パパは自主的に行動することがありますが、その行動に対して過大評価をしないことが大切です。「自分はやったんだから褒めてほしい!認めて欲しい!」といった気持ちは一旦置いておきましょう。
育児は家族全員で取り組むべきものですから、パパの行動も当たり前です。
もちろん家族であっても感謝は必要だと思いますが、感謝の気持ちは自然に育つものです。自然と感謝の言葉がでてくるまでは、自主的な行動自体が足りないのかもしれませんよ。

大切なのは、褒められることや評価を求めるのではなく、赤ちゃんや家庭の幸せを目指して行動することです。家族全員が安心して過ごせる環境を作りましょう。
やってるつもりから抜け出して、家族の幸せを育むために
なぜ、やってるつもりになるのかを書いてみましたが、いかがでしたか?もしいくつか当てはまっていたのであれば、それは家庭の危険信号かもしれません。
育児は、一人ではなく家族全員で取り組むべきものです。パパがママの気持ちに寄り添い、家族全体の幸せを第一に考えて行動することで、育児の負担が軽減され、お互いの信頼感が深まります。育児は単に手伝うものではなく、共に手を取り合い育むものです。
子供をしっかりと見て、ママの声にしっかりと耳を傾け、育児について学び、自主的に行動し、その行動に対価を求めないことが大切です。お互いの小さな成功を認め合い、感謝の気持ちを持つことで、家庭全体の雰囲気が温かくなり、育児そのものがより楽しく感じられるようになるでしょう。
これからもパパとママが協力し合い、共に育児の喜びと困難を共有しながら、より良いパートナーシップを築いていきましょう。
この記事を書くにあたり、以下の文献を参考にしました。
参考文献:J-STAGE 日本保健科学学会誌(産後の妻に対する夫の⽀援に関する国内⽂献検討)
\この記事をシェアする/