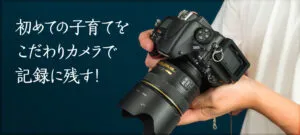赤ちゃんが生まれると、家庭の生活は一変します。
特にママは、出産という大仕事を終えた直後から、体力の回復を待つ間もなく、赤ちゃんのお世話をこなさなければなりません。その中で、パパがどう動くかによって、ママが安心して育児に向き合えるかが決まるのです。
この記事では、産後のママの気持ちや家庭の変化について、パパが知っておきたいポイント&具体的に取り組める8つの行動も紹介しています。
少しずつできることから始めて、ママと家族を支える力になっていきましょう。
目次
なぜ産後の生活は「大きく変わる」のか?
赤ちゃんが家族に加わるのはとても嬉しいことですが、その分、ママの日常にはたくさんの新しい負担が増えます。出産後、体力が戻る間もなく、赤ちゃんのお世話や家事を頑張らなければならない状況が続きます。
パパが「今、何をすべきか」を知ることは、ママの気持ちを理解する第一歩になります。
気づいたら、子どもやママとの距離が広がってる……そんなことになったらやばいよね。
産後はママの体も回復中で、赤ちゃんのお世話も一日中続くにゃ。関心を持たないパパは役に立たないどころか足手まといにゃん。
父親が実感しにくい現実
妊娠すると、ママは自然と「母親になる準備」を始めます。一方で、パパは身体の変化がないため、「赤ちゃんが生まれたら父親になるんだろう」と漠然と考えていることが多いのが実情です。
妊娠中の違い
- ママ: お腹で赤ちゃんを育てる中で、親になる意識が育ちます。
- パパ: 出産が近づいても、「何を準備すればいいか」がわからないままになることが多いです。
産後のズレ
実家に戻っている場合
ママが里帰りしている間、パパが日常的に赤ちゃんと関わる機会が少なくなります。入院中の関わりの不足
出産後の入院期間中、パパが関わる機会がすくないと、退院後の育児に問題が生じる可能性も高くなります。産後すぐのサポート不足
赤ちゃんの誕生直後、パパが「何をすればいいのかわからない」と感じている間に、ママが一人で多くを抱え込むケースがあります。
ズレを感じた場合は、育児書を読んでみることもオススメです。
家事と育児の負担が倍増する現実

赤ちゃんが生まれると、家庭内のタスクは一気に増えます。これまでの「家事」に加えて、「育児」という新しい仕事が日常の中心になるからです。ママが家庭全体の負担を抱え込みやすくなり、ストレスや疲労がたまりやすい状況が生まれます。
家事が増える理由
赤ちゃんがいることで、家庭の中でやるべきことが増えていきます。- 洗濯物が倍増(赤ちゃんの衣類や布おむつなど)
- 部屋の掃除頻度が増加(赤ちゃんが過ごす場所を清潔に保つため)
- 食事準備に手間がかかる(栄養バランスやママの体力回復を考慮)
育児の新たな負担
家事に加え、育児がママの生活に大きな負担として加わります。- 赤ちゃんの健康ケアの必要性
- 授乳(昼夜問わず3時間おきに必要)
- おむつ替え(1日8~10回の対応が必要)
- 夜泣き対応(夜中に何度も起きて赤ちゃんをあやす)
役割分担による偏り
家事や育児を役割として固定化すると、「それはママの担当」という考えが生まれやすくなります。その結果、ママが家庭全体の調整役となり、疲労やストレスが増加します。
ママの体力と精神の負担
出産後、ママの体は産褥期(さんじょくき)と呼ばれる回復が必要な時期に入ります。この期間(通常6~8週間)は、出産による体力消耗やホルモンバランスの変化を整え、体を回復させる大切な時間です。
しかし、その間にも赤ちゃんのお世話は休みなく続くため、体力的にも精神的にも大きな負担がかかります。
体力面の負担
| 負担内容 | 具体的な理由 |
|---|---|
| 産褥期の体のダメージ | 出産で大量の血液を失い、体力が大幅に消耗しています。この回復には通常6~8週間が必要ですが、赤ちゃんのお世話があるため休む暇がほとんどありません。 |
| 睡眠不足 | 授乳や夜泣き対応で夜中に何度も起きる必要があり、まとまった睡眠を取れません。 |
| 腰や肩の痛み | 長時間の授乳や抱っこで、肩や腰に大きな負担がかかり、慢性的な痛みにつながります。 |
| 疲労の蓄積 | 出産の疲れが癒えないうちに、家事や育児が続き、日々の疲労が蓄積していきます。 |
精神面の負担
| 負担内容 | 具体的な理由 |
|---|---|
| 孤独感 | 赤ちゃんと二人きりで過ごす時間が長く、話し相手がいないことで孤独を感じやすくなります。 |
| プレッシャー | 赤ちゃんが泣き止まない時や体調不良時に、「自分が何とかしなければ」と感じてしまい、精神的に追い詰められます。 |
| 頑張りすぎ | 「自分がやらなければ」と無理をしてしまい、休むことに罪悪感を感じることでさらに疲れてしまいます。 |
| 不安感 | 赤ちゃんの健康や成長に対する漠然とした不安が続き、心の余裕を持ちにくくなります。 |
パパが今やるべきこと
ここまでで、ママがどれだけ大変な思いをしているかを、具体的に理解していただけたと思います。出産直後のママは、体力も心も限界に近い状態の中で赤ちゃんのお世話を続けています。この状態を乗り切るためには、パパが積極的に行動を起こすことが必要なのです。
ママが大変なのって、やっぱり出産という大きな出来事があるからなんだよね。
さらに、その後すぐに赤ちゃんのお世話が始まるから、体を休める時間がほとんどないにゃんね。
しかも、赤ちゃんの授乳やおむつ替えは昼夜問わないし、夜泣きだってある。ママにとっては本当に過酷だよね。
だからこそ、パパが家事や育児を積極的にやることで、ママが少しでも体を休める時間を作るのが大事にゃ。
自分の役割を再確認する
赤ちゃん中心の生活が始まる中で、パパが果たす役割も変わります。ママが一人で頑張るのではなく、パパが家庭全体を支える存在だということに自覚を持ちましょう。
ママが安心できる環境を作る
まず、ママが「一人で抱え込む必要はない」と感じられる環境作りが重要です。育児や家事を進んで引き受け、ママに「休んでもいい」「頼れる」と思ってもらうことを目指しましょう。「サポート」ではなく「担う意識」を持つ
サポートに留まらず、「自分が主役として動く場面」を増やしてください。たとえば、夜泣き対応を積極的に受け持ったり、休日の家事を全て引き受けたりするなど、具体的なタスクを進んで担うことが大切です。
頼まれたことを確実にこなす

パパが忙しい中でも、ママから頼まれたことを確実にこなすだけで大きな助けになります。主体的な育児は大切ですが、まずは頼まれ上手になることをめざすと良いでしょう。
快く引き受ける態度を心がける
頼まれた時に嫌そうな態度を見せず、「わかった、やっておくね」と前向きに引き受けることが大切です。頼みやすい雰囲気を作ることが大切です。「やってみる」気持ちが大切
完璧を目指す必要はありません。「まずやってみる」という気持ちで、赤ちゃんのお世話や家事に挑戦するだけで、ママは安心感を得られます。些細な行動でも効果は大きい
小さな行動でも積み重ねることで、ママの負担を大幅に軽減できます。
パパが行動することで生まれる変化
頼まれ上手になれてきたら、次は主体的に動くことを意識してみましょう。自分から行動を起こすことで、家庭には笑顔があふれる家庭円満な変化が生まれます。
ママの心と体に余裕が生まれる
ママの負担が減り、笑顔が増える。結果として育児の時間もより充実したものになります。赤ちゃんとの絆が深まる
赤ちゃんと直接触れ合う時間が増え、パパと赤ちゃんの関係がより強くなります。家庭全体の雰囲気が明るくなる
ママとパパが協力して家庭を支える姿が、家族全体の幸せにつながります。
ママが必要としているやってほしいこと8選
産後、ママがパパに本当にやってほしいことは、大げさなサポートではありません。ママが求めているのは、「日々の生活の中での小さな行動」と「気持ち」の積み重ねです。
ここでは、ママが心から求めている行動を8つのポイントに分けて解説します。
あんまりこんなこと言うと怒られちゃうかもだけど、育児も家事も、ひとつひとつは実は簡単だよね。
でも、それが『毎日続く』『同時にやらなきゃいけない』ってなると、一気に大変になるにゃ。
一つ一つは小さいけど、それが積み重なると本当に大変って事なんだと思うよ。
1. 家事や育児を積極的に受け持つ
赤ちゃんのお世話や家事は、特別なスキルがなくても始められることがほとんどです。
パパが一つずつでも挑戦することで、ママの負担が大幅に減ります。最初は「これならできる」という簡単なことから始めてみましょう。それがやがて自信になり、より多くの育児や家事に積極的に関われるようになります。
- 実践例
- 料理をする。
- 洗濯物をたたむ。
- 掃除機をかける。
- 赤ちゃんのおむつを替える。
- 赤ちゃんのお風呂を担当する。
2. 夜間対応を積極的に担当する
夜中の授乳対応は大変なものですが、パパが夜勤担当をしてくれるとママの睡眠不足が軽減されます。まずは、引き受ける意識が大切です。完ミや混合育児ならミルク作りから、母乳育児であっても搾乳機を導入すれば夜間担当は可能です。
- 実践例
- 夜中に赤ちゃんを抱っこしてあやす。
- ミルクを作る。
- 赤ちゃんが泣き止むまで寝かしつけを試みる。
3. ママの体と心を気遣う
産後のママは体が完全に回復していないため、体力的にも精神的にも負担を感じています。少しの声かけや気づかいが大きな安心につながります。パパの優しい一言や具体的なサポートが、ママに「一人じゃない」と思わせる大きな支えになります。
- 実践例
- 「疲れてない?」「少し休んでて」と家事や育児を引き受ける。
- 赤ちゃんを抱っこしたり遊んだりして、ママがリラックスできる時間を作る。
4. 母親への感謝を伝える
「ありがとう」と言葉で伝えるだけで、ママは「頑張ってよかった」と思えます。日常の中で感謝の言葉を忘れないことが大切です。感謝はママの気持ちを軽くするだけでなく、家庭全体の雰囲気を明るくし、パパ自身の気持ちも前向きになります。
- 実践例
- 「今日もありがとう」と声に出して伝える。
- 赤ちゃんの成長を一緒に喜び、共有する。
5. 育児の知識を積極的に学ぶ
パパが積極的に育児の情報を調べることで、ママが「一人で抱え込んでいる」という負担感が減ります。「知らないから何もできない」という状態を減らし、「自分もできることがある」と思えるようになることが、家族全員の絆を強める一歩です。
育児について学ぶことで、赤ちゃんの成長や健康に興味を持ちやすくなり、パパ自身の育児への関与も自然と深まります。
- 実践例
- 育児本を読む。
- 赤ちゃんの成長についてネットで調べる。
- ママと赤ちゃんの健康について話し合う。
育児書ははじめてママ&パパの育児がオススメです!
6. 自分から率先して動く
まずは「頼まれ上手」になることを目指し、慣れてきたら次のステップとして「自分から動く」ことを意識してみましょう。目に見えることに気づいて動くだけで、ママのストレスは大きく軽減されます。
- 実践例
- 家事育児に主体的に関わる。
- 手が空いている時は、積極的に関与する。
7. ママに一人の時間を作る
ママが心身ともにリフレッシュする時間を確保することは、家庭全体の余裕を生む大切なステップです。パパが赤ちゃんのお世話を担当することで、ママは自分の時間を持てるだけでなく、パパ自身も育児に自信を持てるようになります。
「休日のワンオペ育児」を取り入れることで、ママが思い切り休むだけでなく、パパが赤ちゃんと過ごす貴重な時間を楽しむ機会にもなります。
- 実践例
- 休日に赤ちゃんを連れて散歩に行く。
- 「好きなことしておいで」とママを外出させる。
- 赤ちゃんのお世話をしながら、ママの休息時間を作る。
8. 赤ちゃんの成長を記録する
赤ちゃんの成長はあっという間に過ぎてしまうものです。その一瞬一瞬を記録に残すことは、後で振り返ったときに家族の大切な思い出になります。また、ママが忙しい日々の中で見逃してしまいがちな成長を、パパが記録することで共有し、喜びを分かち合うきっかけにもなります。
- 実践例
- 赤ちゃんの写真や動画を撮影する
- 成長日記をつける(例えば、初めて笑った日や寝返りをした日など)
- 夫婦でアルバムを作成する時間を持つ
本格的なカメラを使えば、より鮮明で美しい記録を残せます。カメラ選びに迷っている方は、関連リンクでおすすめカメラをご紹介していますのでぜひチェックしてみてください。
こちらもどうですか?
ママと赤ちゃんを支えるために、今できることから
この記事では、産後のママがどれほど大きな負担を抱えているか、そしてパパがどのようにサポートできるかを具体的に解説しました。
育児や家事に完璧を求める必要はありません。小さな一歩から始めるだけで、ママの負担が減り、赤ちゃんとの時間がより豊かなものになります。あなたの行動一つひとつが、ママや赤ちゃん、そして家族全体の幸せに繋がります。
ママの大変さを理解したうえで、次のような行動が鍵になります。
家事や育児に積極的に参加すること
赤ちゃんのお世話や家事を分担することで、ママの心と体に余裕を生む。ママへの感謝や気遣いを忘れないこと
小さな声かけや行動が、大きな安心感を生む。パパ自身も育児を楽しむこと
赤ちゃんとの時間を通じて、パパ自身の成長や絆を深める。
少しずつでも行動を積み重ねることで、家族全員が笑顔で過ごせる時間が増えていきます。焦らず、できることから始めていきましょう。大切なのは、「一緒に成長する」という気持ちです。
この記事を参考に、ぜひパパとしての第一歩を踏み出してください。
この記事を書くにあたり、以下の文献を参考にしました。
関西福祉大学リポジトリ(妊娠期から育児期における父親意識と役割行動の獲得に関する文献検討)
\この記事をシェアする/