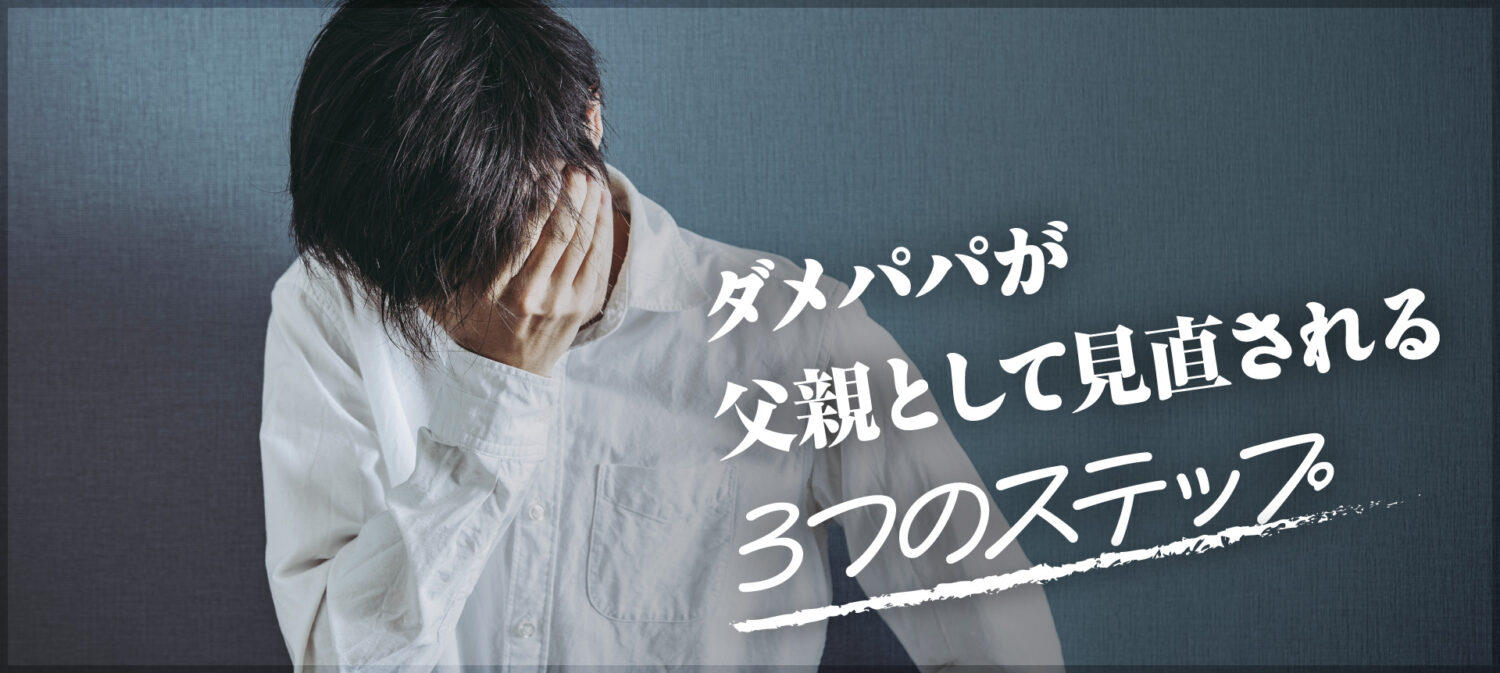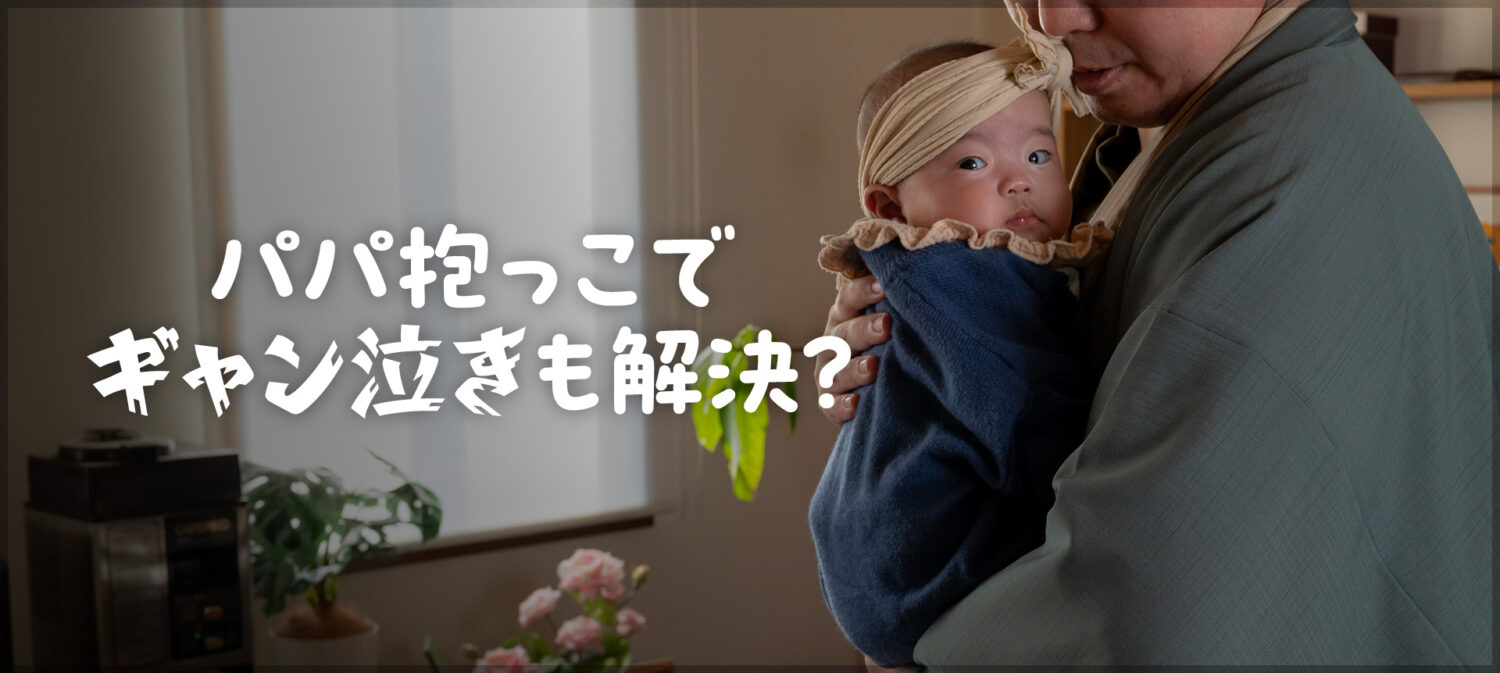6ヶ月頃からパパ見知りが始まることがあります。この時期、赤ちゃんは周囲の人々を意識し始め、赤ちゃんがパパを見るだけで泣いてしまうことがあります。
お父さんとしては、どうして自分だけ?と辛く感じるかもしれません。でも、これは赤ちゃんが成長している証で、一時的なものです。
この記事では、パパ見知りに直面しても気落ちせず、前向きに対応する方法を紹介します。焦らず、赤ちゃんとの信頼関係をゆっくり築くための具体的なステップをお伝えします。
目次
パパ見知りは「失敗」ではない
パパ見知りは赤ちゃんが健全に成長している証であり、決して育児失敗ではありません。パパ見知りが起こる理由と、気落ちせずに向き合うための心構えをお伝えします。
パパ見知りが起こると、ちょっと寂しいよね。でも、これは赤ちゃんが成長してる証なんだよ。
でもパパ見知りって一時的なものだから、焦らず少しずつ距離を縮めていけば大丈夫だにゃん。
赤ちゃんが慣れるペースで関わっていくのがポイントだよ。
パパ見知りは成長の証
パパ見知りは、3~4ヶ月の時期に深く関わりをもつことで避けられることもあります。ただし、仕事が忙しいお父さんにとっては、なかなか時間を取るのが難しく、パパ見知りは避けがたい現象だったりします。
これは決してお父さんのせいではなく、赤ちゃんが成長し、周りの人を認識し始めた証でもあります。
見慣れたママに安心感を覚え、一方でパパに不安を感じてしまうのは自然な反応です。パパ見知りが起きてしまったとしても、焦らず、少しずつ赤ちゃんとの信頼関係を築いていくことが大切です。
とはいえ、パパ見知りが起きてしまうとお父さんとしては寂しい気持ちになるかもしれません。でも、ここで大事なのは、パパ見知りは一時的なものであり、必ず乗り越えられるということです。
もしパパ見知りになったとしても絶対に諦めることなく、少しずつ育児に関わってください。
焦らないことが大事
パパ見知りが起こると、お父さんとしてはすぐにでも赤ちゃんとの距離を縮めたいと思うかもしれません。しかし、焦る必要はありません。パパ見知りは一時的な現象であり、無理に抱っこしたり関わろうとするよりも、赤ちゃんが自然にパパに慣れていくのを待つことが大切です。
無理に距離を縮めない
- 赤ちゃんが泣いている時、無理に抱っこしたり近づこうとせず、少し距離を置いて見守ることも大切です。
- 赤ちゃんがパパに自然と慣れていくために、安心できる環境を作り、無理のないペースで関わりを持ちましょう。
- 家事を積極的に受け持つなど、育児以外の関わり方もあります。家庭円満を意識していれば自然と治まってきます。
少しずつ関わりを増やす
- 最初は短い時間でも、日常の中で少しずつ赤ちゃんと一緒に過ごす時間を増やしていくことが効果的です。
- おむつ替えやお風呂の時間など、赤ちゃんがリラックスできる状況でパパが関わると、徐々に安心感が育まれます。
夜だけパパ見知りってあるの?
昼間は機嫌よくパパと過ごしていた赤ちゃんが、夜になると急に泣き出し、パパの抱っこを嫌がることも少なくありません。夜の時間帯は、赤ちゃんにとって特に不安を感じやすい時間です。

夜だけパパ見知りが起こる理由
疲れや眠気からくる不安感
赤ちゃんは一日の終わりに疲れが溜まり、感情が不安定になりがちです。眠くなると、安心感を強く求め、普段以上にママに依存することがあります。暗く静かな環境に敏感になる
夜は暗く、昼間より静かな環境になるため、赤ちゃんが不安を感じやすくなります。暗闇の中でパパの顔がいつもと違って見えることが、不安の原因になることもあります。
夜だけパパ見知りが起こっても、焦らずに少しずつ慣れてもらうことが重要です。時間をかけて、無理なく赤ちゃんとの信頼関係を深めていきましょう。
パパ見知りが起きた時の具体的な対処法
パパ見知りが始まると、お父さんとしてはどうしていいかわからずイライラしてしまうこともあるかもしれません。
しかし、パパ見知りは一時的なものです。無理に解決しようとせず、赤ちゃんのペースに合わせて接することが大切です。
パパ見知りが起きて、赤ちゃんが泣いちゃうと、つい関わるのを諦めそうになるけど、それは絶対ダメなんだよね。
関わりを続けることで、赤ちゃんもだんだんパパに慣れてくるから、焦らず時間をかけることが必要にゃん。
そうだね。泣かれても諦めずに、少しずつでも赤ちゃんと一緒に過ごす時間を作っていけば、自然と信頼関係ができると思う。
泣いても焦らず、少しずつ信頼を築く
無理に距離を縮めようとせず、焦らず赤ちゃんのペースに合わせることが大切です。
泣かれても、それは赤ちゃんが感情を表現している証拠。お風呂やおむつ替え、寝かしつけなど、リラックスできる時間に少しずつパパが関わることで、赤ちゃんは安心感を得ます。
泣き声を冷静に受け止める
赤ちゃんが泣いてしまっても焦らず、無理に抱っこしようとせず、赤ちゃんが落ち着くまで見守りましょう。泣くこと自体は、赤ちゃんの自然な表現です。少しずつ1対1の時間を増やす
パパがお風呂に入れたり、おむつ替えをするなどの短い時間を積み重ねることで、徐々に赤ちゃんはパパとの時間を楽しめるようになります。遊びやおもちゃを使う
赤ちゃんがリラックスして楽しめる遊びやおもちゃを使って、パパと一緒にいることをポジティブに感じさせましょう。
アンガーマネジメント力を高めるための心構え
パパ見知りが続くと、どうしてもイライラしてしまうことがあるかもしれません。しかし、そのイライラを赤ちゃんにぶつけてしまうことは絶対に避けなければなりません。感情的になりすぎないよう、アンガーマネジメント力を高めることが重要です。
一度深呼吸をして気持ちを落ち着ける
赤ちゃんが泣き止まない時、まずは一度深呼吸をして、自分の気持ちを落ち着けましょう。イライラが募ると、感情的な行動に出てしまうこともあります。深呼吸を繰り返すことで、冷静さを取り戻し、赤ちゃんに穏やかに接することができるようになります。今の状況を冷静に捉える
赤ちゃんが泣いている状況に対して、ただ反応的に怒りを感じるのではなく、泣き止まないのは自然なことであり、赤ちゃんが安心できるまで時間がかかることを理解すると、落ち着いて対応できるようになります。サポートを頼ることを忘れない
お父さんが全てを一人で抱え込む必要はありません。感情が高ぶってきたと感じた時は、ママや家族に助けを求めましょう。赤ちゃんが泣き止まない時や、どうしてもイライラしてしまう時は、一旦パパが引いて、ママに交代してもらうのも一つの方法です。感情的になった時は一旦離れる
感情がコントロールできない場合は、赤ちゃんを安全な場所に寝かせた上で、数分その場を離れて自分の気持ちをリセットしましょう。少し離れることで冷静さを取り戻し、ストレスを和らげることができます。
赤ちゃんが泣き続ける状況に対してストレスを感じることは避けられないかもしれませんが、重要なのは、そのストレスをどうコントロールするかです。
アンガーマネジメントを心がけ、自分の限界を認識し、周りのサポートを活用することで、冷静で優しい対応ができるように努めましょう。間違っても虐待に繋がらないように気をつけましょう。
パパ見知りを乗り越えるために大切な心構え
パパ見知りは、すぐに解消できるものではありません。重要なのは、お父さんが日々赤ちゃんと向き合い続けることと、ママと協力して赤ちゃんに安心感を与えることです。
失敗を恐れず、毎日少しずつ
パパ見知りが起きてしまうと、うまくいっていないと感じることが増えると思います。ただし、毎日少しずつ赤ちゃんと向き合うことで、信頼関係はゆっくりと築かれていくので安心してください。
日常の瞬間をコツコツと大切にしながら、赤ちゃんとの時間を積み重ねていきましょう。
パパとママの協力も大事
パパ見知りが起きている間、お父さんは無理に赤ちゃんとの距離を縮めようとするのではなく、まずはママのサポートに徹することが大切です。
赤ちゃんがママに強い安心感を抱いている時期だからこそ、ママに頼りながら、少しずつお父さんが前面に出る準備をしましょう。
例えば、家事を積極的に担当することで、ママが赤ちゃんに集中できる時間を作ることができます。
ママとパパがチームとして協力し、家事や育児をシェアすることで、赤ちゃんにとってもお父さんが家族の一員であるという認識が深まります。焦らず、ママをサポートしながら、赤ちゃんとの信頼関係を少しずつ築いていくことが、パパ見知りを乗り越える鍵です。
パパ見知りは早い段階なら回避可能!
パパ見知りは、通常6ヶ月頃から始まりますが、実はそれ以前にお父さんが積極的に関わることで回避できる可能性が高くなります。特に3〜4ヶ月の時期に積極的に赤ちゃんと触れ合うことは、パパ見知りを防ぐための大切なステップになります。
パパ見知りの予防は早い段階から
赤ちゃんが生まれてから日々の育児にお父さんも積極的に参加し、赤ちゃんとのスキンシップを増やしておくと、パパ見知りが始まる可能性を大幅に減らすことができます。

お風呂や寝かしつけを担当する
赤ちゃんがリラックスできる時間にパパが関わることが非常に効果的です。お風呂の時間や寝かしつけをパパが担当することで、赤ちゃんはパパとの安心感を深めていきます。抱っこや声かけを積極的に行う
赤ちゃんがパパの声や抱っこに慣れるように、日々の中で積極的に声をかけたり、抱っこする時間を増やしていくことが重要です。短い時間でも、赤ちゃんと直接触れ合うことで、自然に信頼関係が築かれていきます。
パパ見知りを避けたいと考えているお父さんにとって、早期の関わりがとても重要です。この段階でのスキンシップがパパ見知りの予防に繋がるかもしれません。
もっと詳しくパパ見知りを予防する方法について知りたい方は、関連記事で解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
こちらもどうですか?
パパ見知りは一歩一歩乗り越えられる!
パパ見知りは決してお父さんが失敗しているわけではなく、赤ちゃんの成長の証です。
焦らず、日々少しずつ赤ちゃんと向き合い続けることで、信頼関係はゆっくりと築かれていきます。短い時間でもスキンシップを大切にし、無理に距離を縮めようとせず、赤ちゃんのペースに合わせて進めていきましょう。
また、ママと協力して家事や育児をシェアしながら、赤ちゃんに安心感を与えることが、パパ見知りを乗り越える鍵となります。最初は泣かれてしまうかもしれませんが、時間をかけてゆっくりと赤ちゃんとの絆を深めていきましょう。
パパ見知りを予防したい方は、早い段階で積極的に赤ちゃんと関わることも大切です。もしパパ見知りを回避したいのであれば、生まれてすぐから積極的に育児に関わっていきましょう。
この記事を書くにあたり、以下の文献を参考にしました。
参考文献:別府大学・別府大学短期大学部 ジョン・ボウルビィの愛着理論
\この記事をシェアする/