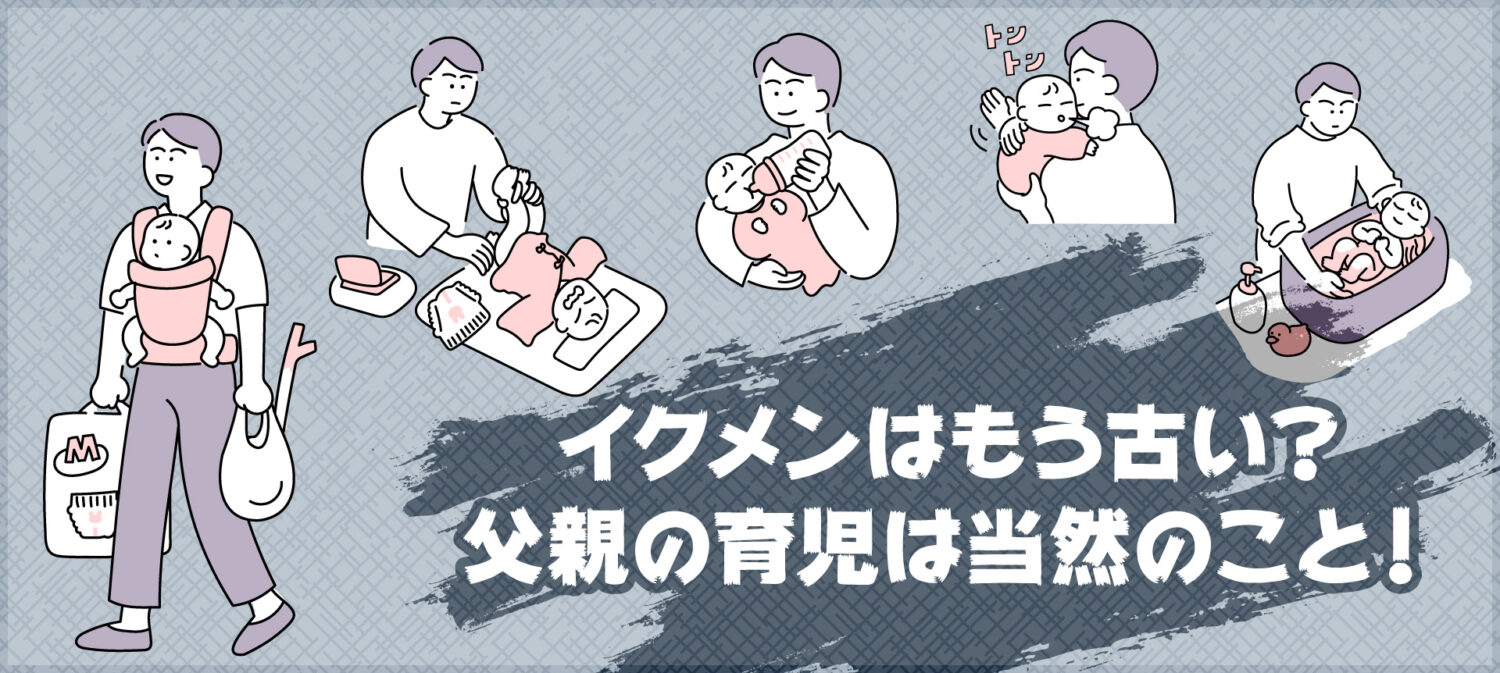最近、イクメンという言葉をあまり聞かなくなった気がします。以前は父親が育児に参加する様子をよく表現していましたが、今は父親も育児をするのは当然と考える方が増えたのかもしれません。
父親が育児に参加するのは、特別ではなく、家族の一員として自然なこと。なのに、なぜこの言葉が生まれ、使われてきたのでしょうか?そう考えると、ちょっと不思議ですよね。
この記事では、イクメンという言葉の背景を振り返りつつ、父親の育児参加がどうして当たり前なのかを改めて考えてみたいと思います。
目次
そもそもイクメンって何?
イクメンという言葉が生まれた背景
イクメンという言葉が広まるきっかけは、2010年に厚生労働省が始めたイクメンプロジェクトです。このプロジェクトは、男性が育児に積極的に参加できる環境を整えることを目的に、父の日に先立ってスタートしました。
特に、男性の育児休業取得を促進するためのキャンペーンが展開され、育児に関わることが男性自身の成長や家族、職場、そして社会全体に良い影響を与えるというメッセージが込められていました。
なぜイクメンという言葉が使われるようになったのか
当時、イクメンという言葉はメディアでも大きく取り上げられ、育児に参加する男性の姿を称賛するムーブメントが広がりました。

今では嫌悪されつつある言葉ですが、男性が育児に参加することは当時まだ一般的ではなく、育児休業を取得する男性も少数派だった為です。そのため、育児に積極的な男性をイクメンとして称えることで、社会全体に男性の育児参加を推奨する空気を作り出すことが、イクメンという言葉に込められていると言えますね。
プロジェクトを通じて、育児は男性にとっても自分自身を成長させ、家族や社会に貢献できる大切な役割であることが強調され、育児に取り組む男性を増やすきっかけとなったのです。
イクメンの登場とその一定の効果
イクメンという言葉が広まった当初、育児に積極的に関わる男性はカッコイイとされ、新鮮で前向きな動きと捉えられていました。冒頭に書いたとおり、男性が育児に参加するきっかけとして、厚生労働省にも利用されてきました。
当時、育児に参加する父親が少なかったことや、育児休業を取得する男性が非常に少数派だったこともあり、結果として、イクメンという言葉によって、男性が育児に参加するきっかけを与えたのは事実です。
時代の進化とイクメンへの違和感
時代が進むにつれて、なぜ父親が育児に関わるだけで特別扱いされるのか、という疑問を持つ人も増えてきました。共働き家庭が増えてきた今、育児は本来家族全体で行うものであり、父親が参加するのは当然のことと感じるのは自然な流れです。
こうした背景の中で、イクメンという言葉が現在も使われ続けることに対しては、父親の育児参加がまだ特別なこととして認識されているのではないかという違和感が生まれるのは当然の流れではないでしょうか?
とはいえ、イクメンという言葉が父親の育児参加を促進する上で果たした役割は大きく、時代の変化とともにその意識も変わりつつあるのです。
育児は性別に関係ない
育児は、本来男女を問わずに関与すべきものです。子育ては、子どもに愛情を注ぎ、成長をサポートする責任を分担するという点では、母親も父親も等しく重要な役割を持っています。
性別によって役割を分けるのではなく、家庭全体で支え合うことが、子どもにとっても、家族にとっても最も自然で健全な形です。
この考え方が広まるにつれ、父親も育児に参加するのは当然だよね、という意識が強まってきました。父親が育児をすることは、母親の手伝いではなく、家族として当然の責務です。
しかし、イクメンという言葉が廃れつつある一方で、現実として男性が主体的に育児に関わる割合はまだ十分とは言えません。イクメンという言葉が今でも使われ続けているのは、まだ社会全体として男性の育児参加が十分に進んでいない背景があるからかもしれません。
父親の育児参加が普通になった理由
女性が働くのが当たり前になったことで、父親が育児に関わるのも自然な流れになってきました。母親だけに負担がかかるのではなく、夫婦で協力して家庭を支える意識が広がってきています。
社会の変化と共働きの増加
共働き家庭が増える中で、父親が育児に参加する機会も多くなりました。
男性は外で働き、女性が家庭を守るという考え方が薄れ、夫婦で家事や育児を分担するのが普通になりつつあります。時代が進む中で、家族の形も変わり、父親の育児参加は自然なものとして受け入れられるようになってきました。
しかし、現実としてはまだ十分ではありません。
父親が育児に参加するメリット
父親が育児に参加することには、家族全体に多くのメリットがあります。父親と過ごす時間が増えることで、子どもはさまざまな視点を学び、情緒も安定しやすくなると言われています。また、父親が育児に関わることで、母親の負担が軽くなり、家庭全体のバランスが取りやすくなります。
さらに、父親自身も育児を通じて家族との絆が深まり、成長や充実感を得ることができます。具体的には、父親が育児に積極的に関わることで、以下のような効果が確認されています。
母親のストレス軽減
父親が育児に参加することで、母親が感じる精神的・身体的な負担が軽減され、母親自身の健康や家庭内の調和に繋がります。子どもの社会的・情緒的発達の促進
父親が育児に積極的に関わることで、子どもはさまざまな視点を学び、自信を持つことができ、情緒的にも安定しやすくなります。父親との関わりが、子どもの健全な成長に大きな影響を与えます。父親自身の成長と充実感
育児に関わることで、父親は家族との絆を深め、自身の成長を感じることができるとされています。家族との時間を共有し、父親としての役割を果たすことで、充実感を得ることが多いです。
父親の育児参加は家庭全体にとって非常に大きなメリットがあるといえます。(参考文献1:「父親の育児参加が母親、子ども、父親自身に与える影響に関する文献レビュー」)
家庭の多様化と父親の育児参加の課題
残念ながら、社会全体で父親が積極的に育児に関わるべきという意識が広まりつつある一方、男性の育児参加は緩やかな増加でしかありません。
厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」では、男性の育児休業取得率は30.1%で、女性の84.1%と比べると大きな差があります。制度は整ってきていますが、男性の育児休業取得はまだ広く浸透していない状況です。(参考文献2:厚生労働省 令和5年度雇用均等基本調査)
イクメンよりも大切なこと
育児は自然な家族の一部
父親が育児に参加するのは、なにも特別なことではなく、家族の一員として自然な流れです。
家族みんなで少しずつ支え合うことで、無理なく日常を回せるようになり、子どもにとっても安心できる環境が整います。お互いが自然に協力し合うことで、家族全体の絆がゆっくりと深まっていく、それが育児の本質ではないでしょうか。
だからこそ、わざわざイクメンという言葉を使って自分を強調する必要はありません。育児は誰かに見せるためではなく、家族の一員として自然に取り組むものだからです。
育児に対する父親の姿勢
父親が育児に関わることを特別にアピールすることは必要ではありません。

育児は、家庭の一員として自然に行うものです。努力をしていることをあえて強調するのではなく、日常的に家族を支える姿勢こそが大切です。母親が育児を無償の愛で行っているように、父親も同じように自然に子どもと向き合い、家族と共に過ごすことが求められています。
育児に対する姿勢が大切であり、それが子どもやパートナーに与える影響は大きいものです。育児をアピールするのではなく、自然に家族と向き合うことが最も重要です。
父親が自然に育児に入るためのヒント
日常の中で育児に参加するコツ
育児は、特別なことではなく、日常の中で自然に取り組むことが大切です。
パパもママも同じように、育児を日常の一部として自然に受け入れることが理想です。たとえば、朝の準備やお風呂に入れるなど、パパができる範囲で積極的に子どもと関わることで、パパとママの役割が自然と平等になっていきます。
無理に完璧を目指すのではなく、家族全員で少しずつ支え合う気持ちが大切です。
パートナーとのコミュニケーションがカギ
育児において、パパとママが平等に育児をシェアしあうには、コミュニケーションが欠かせません。
お互いの役割や負担を話し合い、どのように協力していくかを定期的に確認することが大切です。パパもママも、それぞれの育児の悩みや不安を共有し合うことで、相手の気持ちをより理解できるようになります。育児を協力しながら進めていき、お互いがサポートし合う姿勢が、家庭の安定につながります。
父親ができる具体的なサポート方法
パパが育児に参加する際、ママと同じように育児や家事をシェアすることが大切です。
たとえば、オムツ替えや寝かしつけ、お風呂、子どもとの遊び時間など、日常的にできることをシェアしながら自然に取り組んでいきましょう。育児だけでなく、家事もシェアすることで、パパとママの負担がバランス良く分散され、家庭がスムーズに回るようになります。
分担ではなく、お互いに協力し合いながらシェアするという意識が、家族全体の調和を保ち、日々の生活をより穏やかで楽しいものにしていくはずです。
父親の育児参加はこれからも続く
父親が育児に参加することは、今や特別なことではなく、家族の中で自然な流れとして広がっています。
イクメンという言葉が注目される時代もありましたが、今では父親が育児に関わることをわざわざ特別視する必要はなくなってきています。父親も母親も同じように自然に育児をシェアできる社会が理想です。
イクメンという特別な言葉に頼ることなく、育児が日常の一部として当たり前に行われるようになっていくことが、これからの目標です。育児は誰かが頑張るものではなく、家族全員で協力しながら自然に支え合うものです。
イクメンという言葉が廃れていくように、父親が育児をすることがカッコイイと言われる時代ではなく当たり前になることが求められています。
この記事を書くにあたり、以下の文献を参考にしました。
参考文献1:
J-STAGE 日本公衆衛生雑誌「父親の育児参加が母親、子ども、父親自身に与える影響に関する文献レビュー」参考文献2:
厚生労働省 令和5年度雇用均等基本調査
\この記事をシェアする/