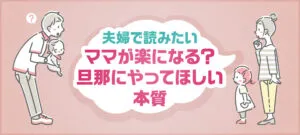赤ちゃんがなかなか寝てくれない……。やらなければならない仕事や家事が山積みなのに、赤ちゃんが泣き止まず、イライラしてしまう。
抱っこしても、おっぱいをあげても、ミルクを飲ませても、寝てくれない……。自分でも信じられないくらいイライラして、手を上げそうになってしまう瞬間さえ……。
この記事では、赤ちゃんが寝ない理由を知りつつ、イライラしないための具体的な方法や考え方のコツをご紹介します。あなたの心が少しでも軽くなり、赤ちゃんと穏やかな時間を過ごすためのヒントをお伝えします。
目次
親の感じるストレスと、赤ちゃんが寝ない理由
赤ちゃんがなかなか寝付かない夜、何をしても寝てくれないと、ストレスを感じてしまうことありますよね。でも安心してください。赤ちゃんの睡眠には、特有のパターンや理由があるのです。
赤ちゃんの睡眠事情を知れば、気持ちが少し楽になります。育児ストレスを軽くするきっかけにしてみてください。
夜中に赤ちゃんが寝てくれずにギャン泣きしてると、ついイライラしちゃうこともあるんだよね。
赤ちゃんも理由があって泣いてるんだってことを知ると、少し気持ちが楽になるかもしれないにゃ。
親が感じる負担とストレス
赤ちゃんが寝てくれなかったり夜中に何度も起きると、親もなかなか眠れなくて疲れがたまりますよね。
「どうして寝てくれないんだろう」と思ううちに、イライラしたり、自分が悪いのではないかと感じることもあるかもしれません。そこから他の家庭と比べてしまうと、「うちだけなんでこんなに大変なんだろう」と落ち込んでしまうことも……。
こうした気持ちは、知らず知らずのうちにストレスを大きくしてしまいます。
イライラを少しでも軽減するためには、まず何が自分のストレスになっているのかを知ることが大切です。原因がわかれば、心の負担を軽くするためのヒントが見えてくるかもしれません。
具体的な育児中のストレス要因
親の睡眠不足
新生児期には3時間ごとの授乳が必要になるため、まとまった休息を取ることが難しくなります。これが続くと疲労が蓄積し、日中の体力や集中力の低下につながります。赤ちゃんの頻繁な泣き声
夜中に泣き続ける赤ちゃんを前に、「どうして寝てくれないんだろう」と焦りや不安を感じる親も多いでしょう。泣き止ませようと試行錯誤を繰り返すうちに、イライラしてストレスが増してしまいます。他の親と比べてしまう
「他の赤ちゃんはぐっすり寝ているのに、どうしてうちの子は寝ないの?」と思うことで、自分を責めてしまうことがあります。この比較が自己肯定感を低下させ、さらにストレスを強めてしまう原因になり得ます。家事・仕事が思うように進まない
寝かしつけに時間がかかることで、家事や仕事が滞りがちになります。「やるべきことが進まない」という焦りが、精神的な負担をさらに増大させることも。時間の不足感
寝かしつけや赤ちゃんの世話に追われ、自分自身の時間を持つことができず、疲労感が解消されないまま日々が過ぎていく感覚が、親のストレスを増幅させる要因になります。役割分担の偏り
家庭内で一方の親に育児の負担が集中することで、疲労感やストレスが高まり、夫婦間の摩擦につながる場合もあります。
こうしたストレス要因の多くは、実は赤ちゃんの寝かしつけに関係しています。もし寝かしつけに成功すれば、役割分担を除くほとんどのストレスが緩和されます。
赤ちゃんの睡眠リズムは未熟
赤ちゃんの睡眠サイクルは大人と比べて未熟で、不規則です。特に生後数か月間は以下の特徴があります

睡眠サイクルが短い
新生児期の赤ちゃんは浅い眠り(レム睡眠)が多く、1~2時間おきに目を覚ますのが特徴です。昼夜の区別がつかない
生後2~3か月までは体内時計が整っておらず、昼夜の区別がつきにくい状態です。成長の一部としての覚醒
空腹や不快感などで目を覚ましやすいですが、これは生存本能と成長に必要なプロセスです。
月齢別の睡眠時間の目安
| 月齢 | 1日の平均睡眠時間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 新生児(0~1か月) | 平均16~20時間 | 短い睡眠サイクルで、1~2時間おきに目を覚ます |
| 生後2~3か月 | 平均15~18時間 | 昼夜の区別がつき始めるが、まだ不規則 |
| 生後4~5か月 | 平均14~16時間 | 昼夜のリズムが徐々に整い始め、夜にまとまった睡眠を取る |
| 生後6~7か月 | 平均13~15時間 | 夜間に6~8時間のまとまった睡眠を取り始める |
| 生後8~9か月 | 平均13~14時間 | 昼寝が1~2回になり、夜間の睡眠が安定してくる |
| 生後10~12か月 | 平均12~14時間 | 夜間に10~12時間の睡眠を取り、昼寝は1回になることが多い |
寝かしつけの工夫
「寝かしつけの工夫なんて、もういろいろ試してるよ……」という方もいるかもしれません。それでも、改めて環境や習慣を見直してみると、新たな発見があるかもしれません。寝かしつけを少しでも楽にするための具体的なアイデアをお届けします。
寝かしつけって、正直『そんなのもう全部やってるよ!』って思うことばかりだよね。
基本はいつでも土台にゃ。赤ちゃんは同じことを繰り返すと安心するから、同じルーティンを続けることが鍵にゃよね。
お風呂や絵本、部屋を暗くして静かな環境を作るとか、当たり前に思えることを丁寧にやるのが大切なのかも。
簡単そうに見えて、それが一番大切にゃよね。
睡眠環境を整える
赤ちゃんが眠るためには、快適な環境を整えることが大切です。以下のポイントを確認して、赤ちゃんがリラックスできる空間を作りましょう。
部屋の明るさ
赤ちゃんが眠りやすくなるよう、部屋を暗くして昼夜の区別をつけやすくします。適切な明るさは、睡眠のリズムを整えるために重要です。適度な静けさ
赤ちゃんが安心して眠れるよう、周囲の音を抑えた静かな環境を心がけましょう。家庭内の生活音にも配慮すると良いです。快適な温度と湿度
赤ちゃんが不快感を感じず、リラックスして眠れる温度と湿度を保ちましょう。適切な目安は、室温20~22℃、湿度50~60%です。
ルーティンを取り入れる
赤ちゃんに「これから眠る時間だ」と感じてもらうためには、毎日のルーティンを決めることが効果的です。ルーティンを繰り返すことで、赤ちゃんは安心して眠りにつきやすくなります。
お風呂
温かいお湯で体を温めることで、赤ちゃんはリラックスしやすくなります。授乳やミルク
お腹が満たされることで、赤ちゃんは眠りに入りやすくなります。絵本の読み聞かせや子守唄
親の声や音楽のリズムは、赤ちゃんに安心感を与えます。静かな声で絵本を読んだり、優しい音で子守唄を歌うと効果的です。ホワイトノイズやBGMを活用する
ホワイトノイズは、赤ちゃんがリラックスするのに役立ちます。また、BGMとして、静かなクラシック音楽や、反町隆史のポイズンもおすすめです。
夜のルーティン例
| 時間 | 活動内容 |
|---|---|
| 19:30 | お風呂で体を温める |
| 20:00 | 授乳またはミルクをあげる |
| 20:15 | 絵本を読むまたは子守唄を歌う |
| 20:30 | 部屋を暗くして、静かな環境で寝かしつける |
ねんねトレーニング(ネントレ)について
ルーティンを整えることは、赤ちゃんが安心して眠れるだけでなく、自分で眠る力を育てる「ねんねトレーニング(ネントレ)」にもつながります。ネントレとは、赤ちゃんが抱っこや授乳なしで眠れるようサポートする方法です。
具体的なネントレのステップとしては、以下のような方法があります:
ベッドに寝かせた後にそっと見守る
赤ちゃんが眠る過程を邪魔しないよう、静かに見守ります。泣いてもすぐに抱き上げない
泣いた場合でも、少し時間を置き、赤ちゃんが自分で落ち着くのを待ちます。ぐずった時はぽんぽん&さすさす
泣いている赤ちゃんを安心させるために、ぽんぽん&さすさすで睡眠を誘いましょう。ルーティンでサポートする
毎日のルーティンを通じて、赤ちゃんの睡眠リズムを整える手助けをします。
無理なく取り組むことを心がけ、赤ちゃんに合ったペースで進めましょう。
便利なアイテムを活用
寝かしつけを助けてくれる便利なアイテムを取り入れることで、親の負担を軽減することができます。赤ちゃんの好みに合わせて、以下のアイテムを試してみましょう。
ホワイトノイズマシン
波の音や心拍音など、赤ちゃんが安心する音を流すアイテムです。周囲の雑音を軽減し、赤ちゃんが眠りやすい環境を作ります。おくるみ
赤ちゃんを優しく包み込むことで、子宮内にいるような安心感を与えます。特に新生児期の赤ちゃんには効果的です。振動マシンやバウンサー
軽い揺れや振動で赤ちゃんをリラックスさせ、眠りにつきやすくします。安全性に注意しながら使いましょう。
イライラを軽減するために親ができること
育児に疲れたとき、イライラした気持ちになるのは自然なことです。でも、少しでもそのイライラを軽くする方法があれば、心が楽になりませんか?親の気持ちを軽くするための考え方や、ストレスを減らす工夫についてお話しします。
いろいろ試してみても寝てくれないときは、どうしたらイライラせずにいられるんだろう……。
それは『この子がここにいること自体が尊い』って思い出すことにゃ。
そうだよね。この瞬間も、赤ちゃんにとってはかけがえのない時間なんだよね。
赤ちゃんが寝る寝ないじゃなくて、一緒にいる時間を大切に思うことが一番にゃね。赤ちゃんが泣いてるのも、生きてる証で、親を必要としてるからにゃよ。
イライラを軽減するための工夫
赤ちゃんの寝かしつけがうまくいかないと、「なんとか寝かせなきゃ」と自分を追い詰めてしまいがちです。しかし、その焦りがさらにイライラを募らせる原因になることも。そんな時は、考え方を少し切り替えたり、行動を工夫することで、気持ちを軽くすることができます。
心の持ち方を切り替えるコツ
「寝なくてもOK」と考える
寝ないことを「ダメ」なことと考えるのではなく、「一緒に居られる時間」と捉えてみましょう。たとえ寝なくても、穏やかな時間を共有できればそれで十分です。優しく抱っこしてあやしましょう。長期的に見守る
赤ちゃんの睡眠リズムは成長とともに少しずつ整っていくものです。「今は寝ない時期なんだ」と、焦らず見守ることも大切です。
ストレスを減らすためのコツ
深呼吸やストレッチを取り入れる
赤ちゃんが泣いていても、親がまず深呼吸で気持ちを落ち着けることが大切です。アンガーマネジメントを意識して、怒りのピークをやり過ごしましょう。イライラを感じたらゆっくり深呼吸をし、冷静さを取り戻す習慣を作ることが有効です。予定を柔軟に調整する
赤ちゃんのペースに合わせて完璧主義をやめるのが大切です。たとえば、家事が少し遅れても問題ないと考えてみませんか?完璧主義を手放し、できる範囲で進めることで気持ちが楽になります。職場に仕事の相談をする
仕事の納期やスケジュールを変更することは難しいと考えがちですが、職場と相談することで柔軟に対応してもらえることも少なくありません。言っても無駄と諦めるのではなく、理解してもらう工夫をしてみましょう。
自分を責めずに育児をする
できる範囲で頑張る
泣いている時間は永遠のように感じるかもしれませんが、長い人生で見れば、ほんの一瞬の出来事です。その一瞬の時間を大切にして、赤ちゃんと過ごす今の瞬間を大切にしてみませんか?赤ちゃんもその瞬間を必要としてくれてますよ。他と比べない
自分たちのペースに合ったやり方を見つけましょう。特にSNSでは、他の家庭が順調で楽しそうに見えることがありますが、隣の芝生は青く見えるものです。良い部分だけを切り取って見せていることもあるので、気にしないのが一番です。自分たちのペースを大切にしましょう。
外部の助けを活用する
育児中、親自身が健康でいることが大切です。一人で抱え込まず、頼れるサービスや人に助けを求めることも考えましょう。
地域の育児支援を活用する
地域の育児相談窓口やサポートサービスを利用してみてください。地域の保育園やこども園などの一般開放に参加するのもオススメです。専門家のアドバイスを受けることで安心感が得られます。産後ケアサービスを利用する
助産師や産院で産後ケアサービスを提供しているところも増えています。食事や育児のサポートを受けられる施設や訪問サービスがあるので、一度調べてみるのもおすすめです。家事代行サービスを利用する
家事代行サービスを利用するのも一つの方法です。掃除や洗濯、料理など、日常の家事を手伝ってもらうことで負担を軽減できます。自治体によっては家事代行サービスの費用を補助してくれる場合もあるので、チェックしてみましょう。リフレッシュの時間を作る
家族や友人に赤ちゃんを預けて、自分のための時間を過ごすことも良いかもしれません。少しでもリフレッシュすることで、育児に前向きに取り組めるようになります。
夫の育児参加を促進する
育児は一人で抱え込むものではなく、夫婦が協力して進めていくことが大切です。夫が家事や育児に積極的に参加することで、母親の負担が軽減されるだけでなく、夫婦間のコミュニケーションも深まります。
特に寝かしつけやギャン泣きなど、親にとって負担の大きい場面では、協力体制が整っているとストレスを大幅に緩和できます。育児を夫婦で一緒に乗り越えることで、お互いの信頼関係も強まり、家庭全体が穏やかな時間を過ごせるでしょう。
夫婦での協力をもっとスムーズに進めるためのヒントが満載です。夫婦の育児に悩んでいる方は、ぜひご覧ください。
イライラしない育児で、赤ちゃんとの時間を大切に
赤ちゃんが寝てくれない夜は、親にとっても大きなストレスです。
ですが、赤ちゃんが寝てくれなくても、今この瞬間がかけがえのない時間であることを忘れずに、赤ちゃんと共に自分自身を大切にすることを心がけましょう。解決になっていないと感じるかもしれませんが、心の持ちようでイライラは軽減し、心にも余裕がもてるきっかけとなります。
育児が楽になるためのポイント
赤ちゃんが寝ないのは成長の一部と捉える
睡眠リズムは少しずつ整っていくものなので、焦らず見守る。イライラを減らす工夫を取り入れる
深呼吸や家族との相談、スケジュールの見直しで負担を軽減する。頼れるサービスや人を活用する
育児支援や家事代行を利用し、一人で抱え込まない。自分を責めずに完璧を求めない
他と比べず、自分たちのペースを大切にする。
赤ちゃんとの育児は、喜びもあれば悩みもあります。
寝ない夜が続くと辛いと感じることもありますが、少しずつ心の負担を軽くする方法を見つけてみてください。赤ちゃんとの時間は短いものです。その一瞬一瞬を大切にしながら、無理のない範囲で育児を楽しむ気持ちを忘れないようにしましょう。
この記事を書くにあたり、以下の文献を参考にしました。
J-STAGE 日本看護科学会誌(産後1か月から4か月までの母親がもつ育児ストレスと対処行動)
\この記事をシェアする/