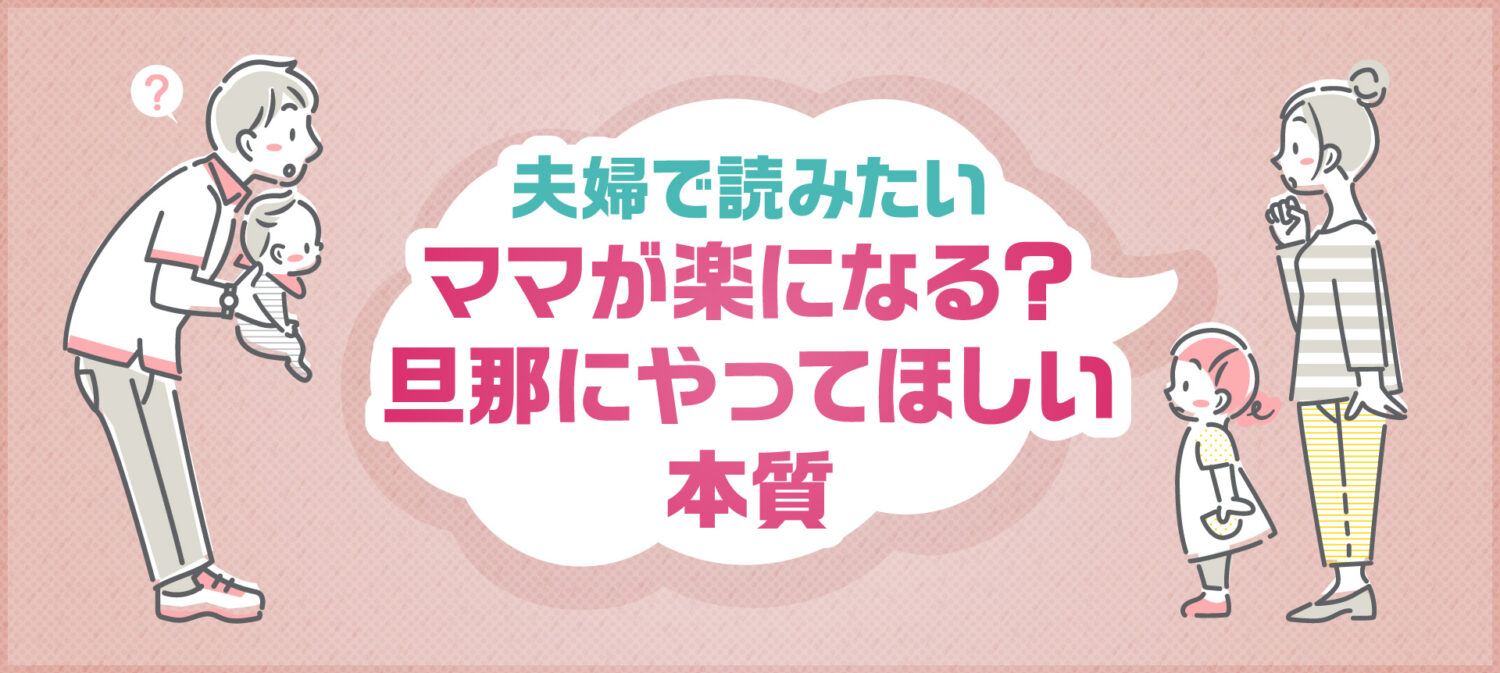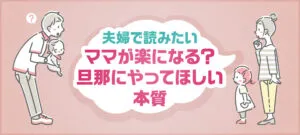育児参加という言葉に、どこか違和感を覚えている人は多いようです。
参加というと、どこか他人事というか、手伝い感覚のように聞こえてしまいますよね。でも、父親が育児に関わることこそが、育児を楽にするための一番の秘訣であり、家族の笑顔や安定を支える大きな力となります。
言葉の違和感にとらわれるのではなく、「父親の育児参加」という言葉をもっと前向きにとらえてみませんか?言葉の違和感を超えた先にある、大切さをご紹介します。
目次
育児参加に違和感を持つ理由とは?
「父親の育児参加」という言葉に、少し無責任な他責思考のイメージを持つ人もいるかもしれません。
でも、父親が育児に関わることで、母親の負担が軽くなり、家族が自然に協力し合える環境が生まれます。家族全員が笑顔で過ごすためにも、違和感を抱く理由を探っていきましょう。
育児に参加って言葉に違和感を感じる人もいるらしいよ。
イクメンは確かに格好つけている印象あったもんね。
育児参加という言葉に感じる違和感
育児参加という言葉に違和感を感じ、どこか他人行儀な印象を受ける人もいるでしょう。
なぜ違和感を感じるかを考えてみると、「参加」が特別視されたり、「手伝い」や「サポート」を意味しているように聞こえるからかもしれません。育児は母親が主体で、父親はその補助をするというイメージが根強く残っているため、違和感と感じやすいのです。
しかし、育児参加という言葉自体が、手伝いやサポートという意味ではないので注意が必要です。
男性が育児に関わることが特別視される背景
父親の育児参加は、家族にとって良いことであり、本来、特別視されるべきものではありません。しかし、父親が育児に関わることが「特別視」されたり、「手伝い」と誤解されがちな背景には、イクメンという言葉の影響があると言えます。
特別視される理由として、以下の点が考えられます。
イクメンという言葉の影響
イクメンという言葉が広まることで、父親の育児が特別な行動のように扱われ、家庭内での自然な役割から外れて見えることがあります。承認欲求やイメージづくり
イクメンが「カッコイイ」「褒められる」存在として注目されることで、育児参加が本来の自然な家族の関わりではなく、周囲から自己アピールと見られることもあります。
父親が育児に関わるのは、家族の一員として当たり前のこと。特別視や称賛されてきた過去が、かえって育児参加を自然なイメージや行動から遠ざけているのかもしれません。
育児参加という言葉への解像度
父親の育児参加へのイメージは手伝いと思われがちですが、解像度をあげて見てみると、父親が積極的に育児に関わることのメリットが浮かび上がります。単純に母親の負担が軽くなり、家庭がより円満になる可能性が高くなるのです。
育児参加に求められるポイント
- 妻の言葉にしっかり耳を傾ける
- 育児の流れを把握し、自然に動く
- 母親の負担を理解し、感謝を伝える
- 必要な場面で自分から行動する
- 母親がリラックスできる時間を意識して作る
- 家事や育児を柔軟に協力し合う
- 互いに思いやりと配慮を持つ
- 家族の安心と笑顔を増やすために行動する
- 仕事も育児をする上で大切
育児参加を言葉狩りせずに、もっと積極的に受け入れよう
父親が積極的に参加する姿勢をみせることは、家庭に安心感が生まれ安定するきっかけになります。育児参加を家族全体で前向きに捉え、家族みんなで支え合う体制を考えてみませんか?
「父親の育児参加」という言葉自体を否定するのは、ちょっとやり過ぎだよね。
そうにゃん。家族みんなで協力するのが一番大事なんだから、言葉にこだわらなくてもいいにゃん。
お父さんが自然に関わることで、家族全体が安心して過ごせるのが理想にゃ。
仕事で家庭を支えることも立派な育児の一環
よく批判されがちですが、父親が仕事で家族を支えることも、大切な育児の一部です。

日々の生活を守り、子どもの将来のために働く姿勢は、立派な育児といえるでしょう。仕事だってストレスが溜まることも多いので、お父さんの頑張りにも理解を寄せ、家族全員で支え合えるのが理想です。
仕事と育児のバランスを意識しながら、家族全員が無理なく協力できる環境を目指していきましょう。
育児参加が父親の関与を促し、家庭の安定を生む
令和3年社会生活基本調査結果を見ると、夫の家事育児参加は年々伸びているものの、妻の負担は相変わらず多大な状況が続いています。だからこそ育児参加という言葉尻をつかまえて、批判をするのは誰も得をしない状況でした。
夫と妻の家事関連時間をみると、夫は1時間54分、妻は7時間28分となっており、2016年と比べると夫は31分の増加、妻は6分の減少となっている。
出典:(「令和3年社会生活基本調査結果」(総務省統計局))
父親の育児参加という言葉は、その言葉通り父親が育児に「参加」することです。育児参加を前向きに受け入れることで、父親が育児に関わる機会が増えていきます。
大切なのは、家事育児時間を延ばすことです。言葉狩りをしたとしても、現実的な家事育児時間は増えないので、ぜひ積極的に育児参加を謳っていきましょう。
父親の育児参加が生む具体的な効果
父親が育児に積極的に関わることで、家庭には多くのメリットが生まれます。母親の負担が軽減されるだけでなく、子どもや家庭全体がうまくいくのです。
母親の負担軽減
父親が日常的に育児に関わることで、母親が抱え込む負担が減り、家庭内で調和が生まれます。子どもに安心感が生まれる
父親が自然に関わることで、子どもも日常的に家族からの支えを感じ、家庭内に安定感が生まれます。家族全体の信頼関係が深まる
家族全員が協力する姿勢が強まることで、家庭内での信頼が育まれ、安定した環境が築かれます。
第三者の視線より、家庭内の笑顔を大切に
育児参加という言葉に違和感を持つ人もいるかもしれませんが、積極的に育児参加がおこなわれている家庭は、幸福感が自然と高まるものです。
たとえ言葉に違和感があっても、夫婦で協力し、コミュニケーションを続けることが何より大切です。育児参加が家庭の一部として根づき、家族が笑顔で過ごせる日々を目指していきましょう。
育児参加によって得られる「シェア育児」の効果
育児参加は父親が主体的に関わるべきですが、育児の中心が母親になりがちなのは、多くの家庭で見られる現実です。だからこそ、出産後は母親が「司令塔」として家庭を支える場面が増えていきます。
ママは育児をシェアして、パパがしっかり受け持つ姿勢は大切だよね。
にゃるほどにゃ。ママが安心してシェアできるように、パパが頼りになるのが理想にゃんね。
さらにお互いに感謝し合えると一番だね。
出産や母乳育児は母親にしかできないこと、だからこそ夫がしっかり支える姿勢が大切
出産や母乳育児は、どうしても母親にしかできない役割です。だからこそ、夫がその負担を支え、家庭全体をサポートする姿勢が大切になります。
「サポート」や「育児参加」という言葉は、どこか受け身に聞こえるかもしれませんが、母親はできる限り家事や育児をシェアし、父親は柔軟にそのシェアを受け持つ姿勢が求められます。こうした協力体制が、家族全体の安心と調和を生むのです。
夫婦がお互いを支え合う姿勢を大切にし、よりよい家庭づくりを目指していきましょう。
シェア育児のポイント
家事や育児を分担してしまうと、協力体制が分断される可能性が高くなります。
大切なのは、母親がシェアしやすい環境をつくること。父親が必要な場面で自ら行動することで、シェアされた家事育児を受け持ちやすくなります。結果として負担が自然に分散され、理想的なシェア育児の環境が築かれます。
- 母親が中心であることを肯定的に受け入れる
- 母親の指示に柔軟に応え、家族を支える姿勢を持つ
- 感謝を伝え合いながら、家族全員で協力する雰囲気を育む
シェア育児は家庭の基盤を強化し、父親の主体的な育児参加に繋がります。下記の記事も参考になると思いますので、興味があれば是非読んでみてください。
こちらもどうですか?
父親の主体的な参加とシェア育児の実践
大切なのは家事や育児を「やらされている」と感じるのではなく、自然に前向きに取り組むことです。少しずつでも父親が育児や家事に時間をかけていくと、自然とスキルが身につき、母親の負担も軽くなります。
積極的な育児参加の姿勢は、夫婦がお互いを支え合う土台となり、家族全員が協力し合える家庭づくりを進めてくれるでしょう。
家庭と社会の両方で、父親の「育児参加」を当たり前にしよう
父親の育児参加が特別視されることなく、家庭や社会で当たり前になることで、家族全員が無理なく協力し合える環境が整います。堂々と「育児参加」を掲げ、家庭と社会で育児をシェアできる未来を築いていきましょう。
父親の育児参加が、家庭でも社会でも当たり前になれば、みんな無理なく協力できる環境が整うよね。
そうにゃんね。父親の育児参加はもっと増えて欲しいにゃんね。
育児参加が自然と広がる社会と家庭を目指して
育児参加という言葉に違和感を感じるよりも、自然と受け入れる社会が理想です。父親が自然に育児に参加することで、育休も取得なりやすくなるでしょう。そうなれば、母親に重くのしかかっていた「つらくて大変」という負の感情も薄れていきます。

また、家事・育児は日々の積み重ねで身につくもので、ひとつひとつは難しいことではありません。ぜひ積極的に参加して身につけていきましょう。
育児は日々の小さな一歩から
育児は身についていくもの
少しずつ慣れていくことで、家族の自然な支え合いが育ちます。育児の喜びを共有
難しい場面もあるかもしれませんが、子どもの成長を見守る喜びは何にも代えがたいものです。
私自身、育児をしていて大変だと感じる瞬間は確かにありますが、それ以上に、子どもの成長は何にも代えがたい幸せの象徴です。大変さをはるかに上回る喜びと楽しさがあります。
父親の育児参加が当たり前になれば、大変という気持ちよりも、育児が楽しいと思える人が増えるのではないでしょうか?こうした家族の笑顔が広がる未来を目指していきましょう。
育児参加を積極的に受け入れて、家庭円満な未来へ
育児参加という言葉に違和感を感じることもあるかもしれませんが、父親が自然に育児に関わることが、家族みんなの笑顔と安心を支える土台になります。
言葉のもつ意味を深く考えすぎず、前向きに取り組むことで、家庭内で支え合い、子どもの成長を喜び合える環境が整います。
育児参加は特別な行動ではなく自然な協力
「手伝い」ではなく、共に育児を担う意識を
お父さんの仕事も、家庭を支える大切な育児の一環
外部の意見よりも家族の笑顔を大切に
育児は経験を通じて自然に慣れていくもの
育児の喜びを家族全員で共有する
育児参加を前向きに受け入れることで、家族全員が無理なく協力しあえます。家庭円満を目指して積極的に受け入れていきましょう。
この記事を書くにあたり、以下の文献を参考にしました。
参考文献:J-STAGE 生活協同組合研究(父親の家事・育児への参画と楽しい食生活)
\この記事をシェアする/