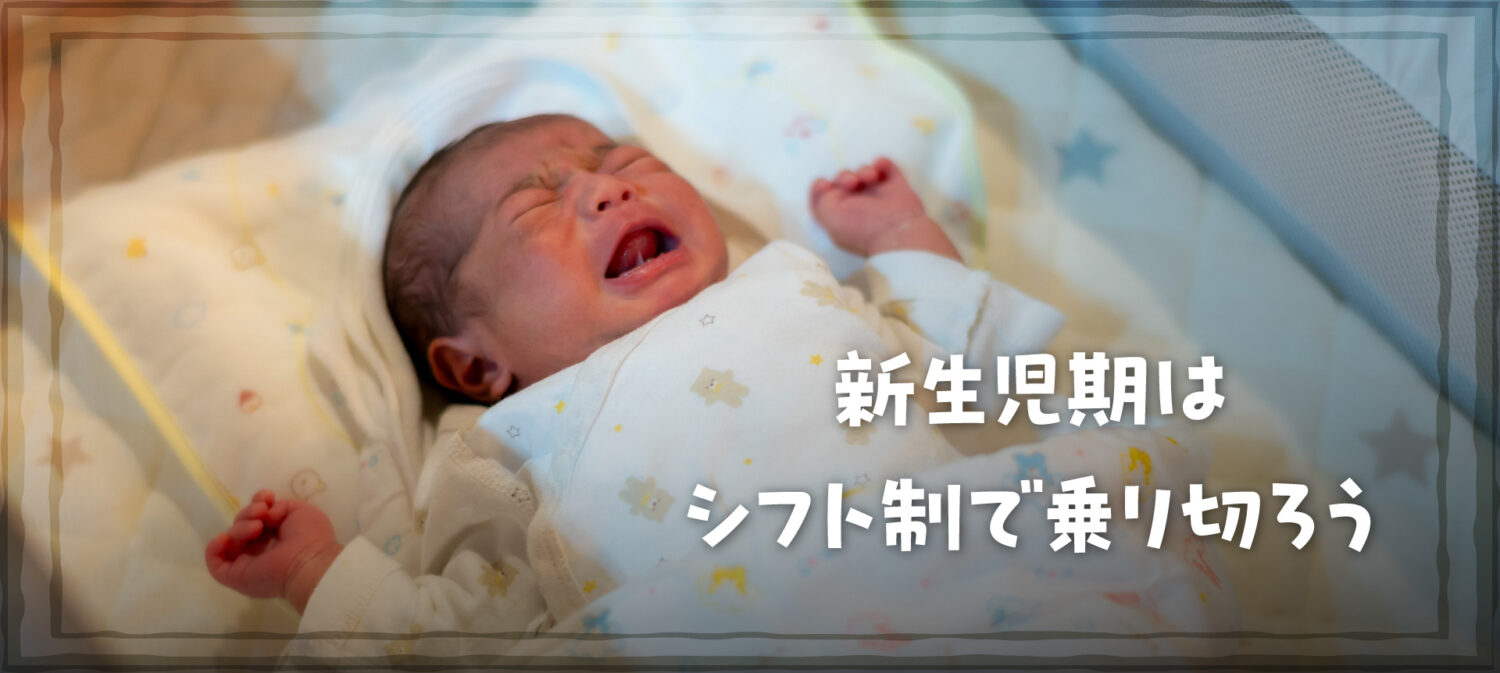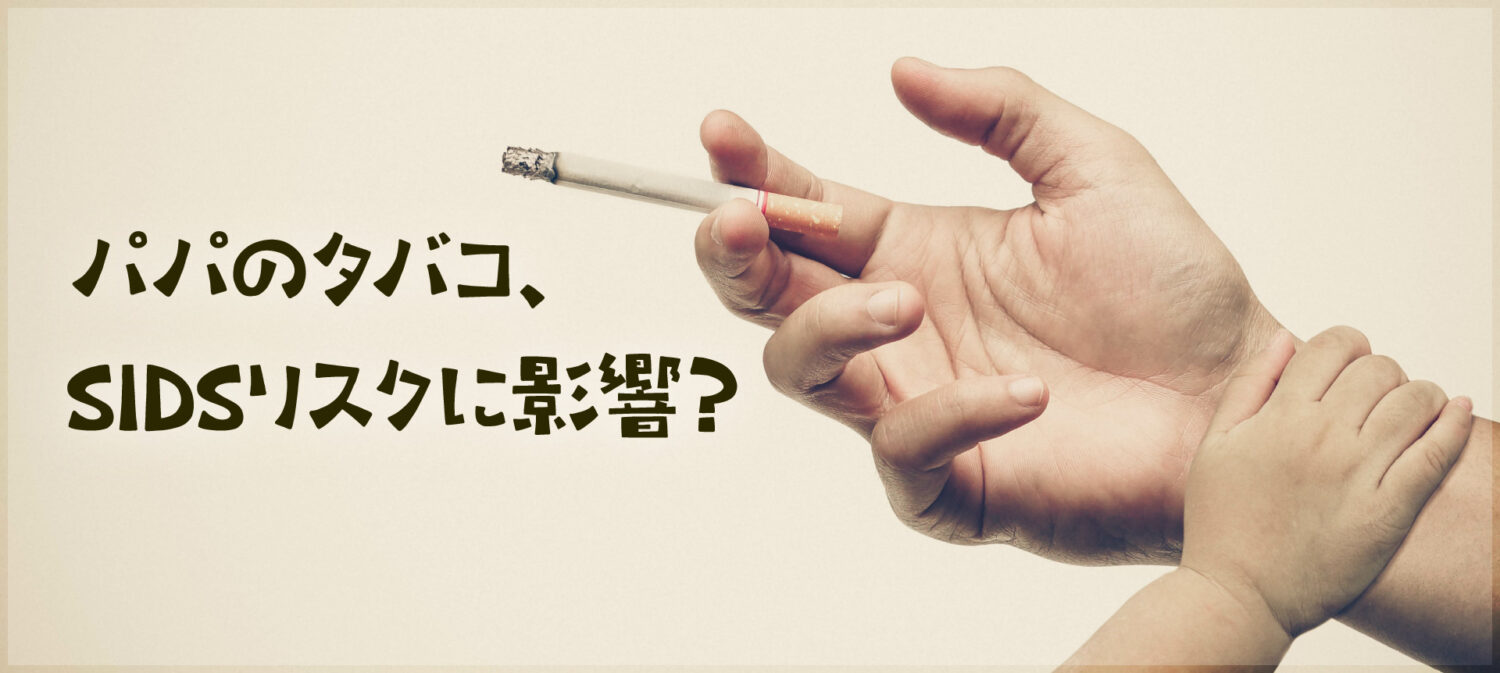育児をしていると、なぜか旦那に「ずるい!」と感じてしまう瞬間が多々ありますよね?
こうした不満が積もると、ストレスやモヤモヤが増えてしまいがちです。そこで今回は、育児中にママが感じやすい「ずるい!」の瞬間を7つに分けて深掘りし、それぞれの解決策や気持ちの整理法についてご紹介します。
少しでも気持ちが軽くなるようなヒントをお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
育児中の「ずるい!」を感じる瞬間とは?
育児や家事に忙しい毎日の中で、「どうして私ばかり……」と旦那に対して「ずるい!」と感じる瞬間がある方も多いのではないでしょうか?一つひとつは小さな不満でも、こうした気持ちが積み重なると、ストレスやモヤモヤが増していきます。
例えば、次のような場面で「ずるい!」と感じることが多いかもしれません。
育児や家事で、つい『なんで私ばっかり…』って感じること、あるにゃん。
そうなんだよね、ちょっと「ずるい!」って思っちゃう気持ちはわかるよ。
小さな不満が積もると、いつの間にかストレスになるにゃ。
ずるいと感じるあるある7選
育児をしなくても許されるのはずるい
- 子どもが夜泣きしても、旦那はそのまま寝続けている
- 子どもがぐずっているのに、旦那はスマホを見てリラックスしている
- 休日も旦那は自分の時間を楽しみ、育児には参加しない
自由時間があるのはずるい
- 旦那が仕事後や休日に趣味や友人と過ごす自由時間を持っている
- 子どもが寝た後、旦那がリラックスタイムを楽しんでいる
- 休日に旦那が一人で出かけてリフレッシュしている
家事も育児も手伝えばいいと思っているのはずるい
- 旦那が「おむつ替えを手伝ったから十分」と言い張る
- 旦那が食器を洗っただけで満足している
- 週末に数分だけ子どもと遊んで「手伝った」と思い込んでいる
子どもはママに任せておけばいいと思っているのはずるい
- 子どもが泣くたびに旦那が「ママに任せる」と言ってくる
- 子どもの予定や体調管理をすべてママが担当している
- 子どもの学校行事や友達関係についても無関心でいる
自分の体調を優先できるのはずるい
- 旦那が体調不良のときは休めるが、ママは具合が悪くても休めない
- 旦那が少し体調を崩しただけで大事にされるのに、ママは我慢している
- 旦那が風邪をひくと全ての家事・育児が免除される
少し家事育児をしただけで過大評価されるのはずるい
- 旦那が少し家事自慢をしただけで「すごいね」と言われる
- 旦那が「イクメン」と評価される
仕事を理由にすれば全てが許されるのはずるい
- 旦那が「仕事だから」として家事や育児を免除される
- 仕事を理由に自由な時間を確保している
- 旦那が仕事を理由に、家族イベントや予定から離れがちになる
夫の行動が原因?「ずるい!」と感じる瞬間とその解決策
育児や家事の中で、なぜか夫に「ずるい!」と感じてしまう瞬間があるかもしれません。
夫が育児や家事の一部だけを「手伝う」姿勢にとどまっていると、家庭全体のバランスが崩れがちです。ここでは、夫の行動が原因で「ずるい!」と感じる具体的な場面と、家庭全体で協力し合うための解決策を紹介します。
育休が取れたから家族と一緒にいられたけど、もし取れなかったら……。
育児を一人で抱えるのはやっぱり大変だし、不満は溜まってた可能性高いかもにゃ。
うん、本当にその通りだよ。もしワンオペだったら、ズルいって思う気持ちすごくわかるもん。
1. 育児をしなくても許されるのはずるい
- 妻が家庭全体の調整を担っている
夫が担当外と考える家事育児には関与しないため、最終的に妻が全体の育児バランスを取る役割を負担している。 - 夫が「自分の担当だけ」に満足し、それ以外に無関心になりやすい
自身の担当範囲だけで満足するため、結果として負担の偏りに無関心になりがち。
- 「どちらかが担当する」から「双方がサポートし合う」意識へ転換する
家事や育児の「責任者」を固定せず、日々のタスクを共に見渡しながら交互にサポートし合う体制を作ります。例えば、夜間の対応を週ごとに交代するなど、役割を柔軟にシフトすることで妻が抱え込まないよう工夫します。 - 家庭全体の「見える化」を行い、全体で役割を共有する
週ごとに家事や育児のリストを共有し、夫が家庭全体の流れを把握できるようにします。リスト化により「誰がどれを担当するか」ではなく、「どこで協力が必要か」を常に見渡せる仕組みを構築します。 - 定期的な進捗チェックと調整タイム
週末に家事や育児の負担が偏らないよう、進捗を共有する時間を設けます。進捗確認の時間を作ることで、夫も家庭全体にどのようなサポートが必要か把握しやすくなります。
2. 自由時間があるのはずるい
- 夫が自分の自由時間だけを確保し、家庭内のサポートを後回しにしている
夫が自身の自由時間を優先し、家庭内のサポートを後回しにしているため、負担が偏っている。 - 妻のリフレッシュ時間がない
妻が家事や育児に追われて自分の時間をもてない状況になっている。結果として夫だけが自由な時間を楽しむ状況になっている。
- 自由時間の交互確保ルール
夫婦で交代制の自由時間を取り入れ、どちらも育児や家事から一時的に離れる時間を確保します。たとえば、週末は「夫が午前、妻が午後」などの分け方を提案し、互いに休息できるようにします。 - 日常のサポート体制を細分化してシェア
自由時間が取りにくい場合でも、平日夜の10分だけ妻のリフレッシュタイムを設け、夫がその間の家事や育児を担うなど、互いにフォローできる体制を作ります。 - 休息や自由時間について話し合い、互いの時間を尊重する意識を持つ
夫婦で「お互いがリフレッシュすることで家庭全体に良い影響がある」と話し合い、どちらの時間も尊重できるように心がけます。
3. 家事も育児も手伝えばいいと思っているのはずるい
- 夫が家事や育児を「自分が少し手伝えば十分」と捉え、全体の流れを見ていない
夫が家事や育児を一部だけ手伝えば十分と考え、全体の流れや負担を把握していない。 - 夫の分担意識が強く、妻に最終的な全体の管理を押し付ける形になっている
夫が分担意識を強く持ち、結果的に妻が全体の管理を任される状況に陥っている。
- 家事・育児の進捗と役割を可視化し、全体を共有する
家事や育児の全体像をリスト化し、妻の負担を夫がしる努力をしてみてください。 - 分担から「協力」へシフトし、担当制を避ける
特定の役割に固定するのではなく、その場に応じて協力する意識を育てます。 - 小さなサポートでも「お互いを認め合う」習慣を持つ
家事や育児の成果が目立たなくても、互いの行動に「感謝」を示し合う習慣を心がけます。些細なサポートも認めることで、家庭全体で協力する雰囲気を築きます。
4. 子どもはママに任せておけばいいと思っているのはずるい
- 夫が育児に関して「ママに任せておけば大丈夫」という固定観念を持ち放置している
夫が「ママに任せておけば大丈夫」という固定観念から、育児の計画や管理をすべて妻に依存している。 - 全ての育児を、妻に丸投げしている
夫が育児に無関心で、妻がすべての育児管理・対応を担う状況になっている。
- 育児や家事の管理を夫婦で「見える化」する
子どものスケジュールや家庭内の育児計画をカレンダーや共有アプリで見える化し、夫もその場でスケジュールを把握できるようにします。夫が管理に関わることで、育児の責任を共有しやすくなります。 - 育児の定期的な話し合いで「協力体制」を構築
子どもの成長や予定、健康状態について週に一度話し合う時間を設け、夫も育児の現状を把握し、必要なサポートを考える機会を作ります。 - 夫が「親としての役割」を持つ場を増やす
夫に「任せている」部分ではなく、彼が「主体的に関与できる」場を意識して設けます。たとえば、病院の予約など、夫が積極的に関わりやすいところを任せてしまい、育児の全体像を意識できるようにします。 - 子どものケアにおいて「日常的なサポート」を夫に求める
子どもの日常のケアに関しても、「お風呂に入れる」「寝かしつける」など、夫が毎日行うタスクを設定し、子どもとの関わりを深められるようにします。役割が増えることで、家庭全体の育児への意識も高まります。
5. 自分の体調を優先できるのはずるい
- 自分の体調を優先し、妻の体調管理を意識していない
夫が自分の体調を優先し、体調が悪いときには休む一方で、妻の体調管理には無関心である。 - 妻が体調を崩してもサポートがない
妻が体調を崩しても夫からのサポートがなく、夫が健康を優先する中で妻が無理をして対応している。
- お互いの体調を大切にする
夫婦で体調が悪い時には交代でサポートし合うことを前提とし、具体的な対応策を決めます。たとえば、片方が体調不良なら、もう片方が育児や家事を担う体制を整えます。 - 「体調不良時の対応リスト」を用意する
急な体調不良でも家庭が回るよう、あらかじめ対応リストを作成し、夫が積極的にサポートできる環境を整えます。これにより、妻が体調不良時に安心して休めます。 - 日常の中で「無理をしない日」を設ける
夫婦で週に一度「無理しない日」を設け、交代で休息を取る習慣を導入します。家族全体で体調を気遣い合う意識が根付き、妻が一人で負担を抱える状況を防ぎます。 - 定期的な健康チェックと家事・育児のシェア
定期的に夫婦で体調をチェックし合い、状況に応じて家事や育児のシェアを再調整します。
6. 少し家事育児をしただけで過大評価されるのはずるい
- 夫がわずかな家事・育児に参加するだけで満足
夫が少し家事や育児に参加するだけで満足し、妻の負担が当たり前のように扱われている。 - 夫が「イクメン」として周囲に称賛されている
夫が「イクメン」として称賛される一方、妻の継続的な努力が軽視されがちである。
- 家事・育児の役割分担を可視化し、夫婦で成果を共有する
家事や育児の具体的なタスクリストを夫婦で共有し、日常的に行われている作業量を明確にします。夫が「少しだけ関わっている」という感覚を払拭し、日常の協力を実感できる体制を作ります。 - 「ありがとう」と感謝を伝え合う習慣
夫が家事や育児に関わった際はもちろん、妻の日常の取り組みにも積極的に感謝の言葉を伝え合います。小さな行動にも感謝を示すことで、互いの努力を認め合う雰囲気が家庭に広がります。 - 毎週の家事・育児の進捗確認で互いの役割を認識
家事や育児の進捗を毎週確認し、現状の負担や必要なサポートを夫婦で共有します。こうした共有の時間を設けることで、夫が「少しだけ手伝えばいい」という意識を改め、協力の継続を促します。 - 家事や育児を「シェアし、受け持つ」体制を築く
妻がすべてを抱え込まずに済むよう、夫が家事や育児を「手伝う」ではなく「受け持つ」姿勢を意識することが大切です。まずは妻が家事や育児のシェアを意識し、夫がその役割を自ら受け持ちやすくする協力体制を作りましょう。
7. 仕事を理由にすれば全てが許されるのはずるい
- 夫が「仕事だから」と家事や育児から免除される傾向がある
夫が「仕事だから」との理由で家事や育児から免除され、妻に負担が偏る状況になっている。 - 夫が仕事を家庭より優先し、妻の負担を無意識に増やしている
夫が仕事を優先することで、結果的に妻の負担が増えている。
- 仕事のストレスを理解しながら、夫が受け持ちやすい体制にする
仕事のストレスを共有するのも大切です。その上で、「子どものお風呂入れ」や「寝かしつけ」など、夫が参加しやすい育児の体制を整えましょう。 - 家庭での貢献が実感できる時間を持つ
夫が「仕事だけでなく家庭でも貢献している」と実感できるようにします。例えば、週末はワンオペ育児をし、妻が休める時間をつくるのも良いかもしれません。
夫に原因がない?それでも感じてしまう不満の対処法
夫は家事や育児に協力してくれているはずなのに、なぜか不満を感じてしまう瞬間があります。こうした感情が積み重なると、協力体制を築く上での障害になることが考えられます。
ここでは、妻が無意識に抱えがちな不満が協力体制にどのような影響を与えるかを見直し、気持ちを整理する方法について考えて行きましょう。
SNSで『夫はよくやってる方だけど、やっぱり不満がある』っていう話をたまに見るんだけど、もう少し認めてあげたらいいのに……って思うことがあるんだ。
うん、ちゃんと協力してる部分があるなら、それも大事にしたいところだにゃ。
そうなんだよね。ちょっともったいないなぁって思ったりはするよ。
1. 他の家庭と比較して「うちの夫は物足りない」と感じる
不満を感じる瞬間
- 他の家庭の夫が積極的に家事や育児に参加している話を聞くと、「うちの夫ももっと協力してほしい」と感じてしまう。
- 友人やSNSで「理想の家庭」の話を目にするたびに、夫に対する理想と現実のギャップに不満を抱いてしまう。
本質的なリスク
- 他の家庭と比較することで、自分たちの家庭の良さやペースを見失い、夫が十分に協力していても物足りなく感じてしまうことがあります。また、比較によって高まった理想が、現実の夫に対する不満や苛立ちを増幅し、信頼や協力体制の構築を妨げる原因になる可能性があります。
対処法
- 「他の家庭がよく見えるのは当然」と理解する
SNSでは表面的によく見せている場合も多いですが、実際にはどの家庭にもそれぞれの課題があります。他の家庭と比較するのではなく、自分たちのペースや価値観を大切にしましょう。 - 夫婦で自分たちに合った協力体制を整える
自分たちの家庭に合った協力体制を見つけるために、夫婦で定期的に話し合いを持ち、理想と現実のバランスを見直します。
- 「他の家庭がよく見えるのは当然」と理解する
2. 夫が努力してくれても「自分ばかり負担が多い」と感じる
不満を感じる瞬間
- 夫が家事や育児に協力しているのに、どこか「もう少し頑張ってほしい」と物足りなく感じてしまう。
- 家事や育児を手伝ってくれても、「もっと積極的に動いてほしい」という気持ちが湧いてくる。
本質的なリスク
- 夫が十分に協力しているにもかかわらず、「もっと」と感じてしまうと、夫婦間に摩擦が生じやすくなります。また、理想と現実のギャップが広がることで、夫への不満が蓄積し、協力体制に支障が出る可能性があります。
対処法
- 夫の取り組みに感謝を示す
夫が努力している点に目を向けて、「ありがとう」という感謝の気持ちを伝えることで、夫婦間の信頼関係が深まります。 - 理想と現実のギャップを見直す
理想と現実の違いを受け入れ、期待しすぎるのをやめましょう。夫婦が無理なく協力し合える環境を大切にします。
- 夫の取り組みに感謝を示す
3. 夫にもっと自分の負担を理解してほしいと感じる
不満を感じる瞬間
- 自分の負担を「もっと分かってほしい」と思ってしまうが、夫にそれを全て察してもらうのは難しいと感じる。
- 自分が経験した大変さについて、夫が十分に理解できていないと感じる。
本質的なリスク
- 「もっと理解してほしい」と思う感情が積もると、夫に対する不満として現れやすくなります。これにより、協力体制に亀裂が生じ、期待と現実のギャップが原因で不満が蓄積する可能性があります。
対処法
- 気持ちを具体的に伝える
夫に期待するのではなく、具体的に自分の気持ちや体験を伝えることで、夫も理解しやすくなります。 - 全てを理解してもらおうとせず、必要な協力をお願いする
感情の全てを理解してもらうのではなく、「ここだけはサポートしてほしい」と協力を依頼し、夫が関わりやすい体制を整えます。
- 気持ちを具体的に伝える
家庭円満のために必要な「お互いを理解する姿勢」
日々の育児や家事で「ずるい!」と感じる瞬間は、誰もが経験するものかもしれません。しかし、その不満を乗り越え、お互いの役割を尊重しながら家庭を築いていくためには、協力し合う意識と心からの感謝が大切です。
育児や家事をよりスムーズに分担・協力するための具体的なポイントを以下にまとめました。
夫が原因の「ずるい!」に対して
- 役割を固定化せず、どちらも積極的に家庭をサポートする「シェア」の意識を持つ
- 家庭内の状況を可視化し、お互いが関わりやすいタスクを共有する
- 夫が主体的に関わる機会を増やし、妻の負担が偏らない体制を整える
妻が感じる不満に対して
- 自分たちのペースを大切にし、他の家庭と比較せずに自分たちの価値観を再確認する
- 夫に期待しすぎるのではなく、具体的にサポートしてほしい部分を伝える
- 理想と現実のギャップを見直し、現状に感謝を示し合う
家庭を支えるには、理想的な分担よりも「柔軟な協力体制」を築くことが鍵です。
些細なことでも感謝を示し合い、負担を軽くするためのシェアの意識を持つことで、毎日が少しずつ快適で心地よいものになります。夫婦で力を合わせ、協力し合いながら、互いに心地よい家庭を目指していきましょう。
\この記事をシェアする/