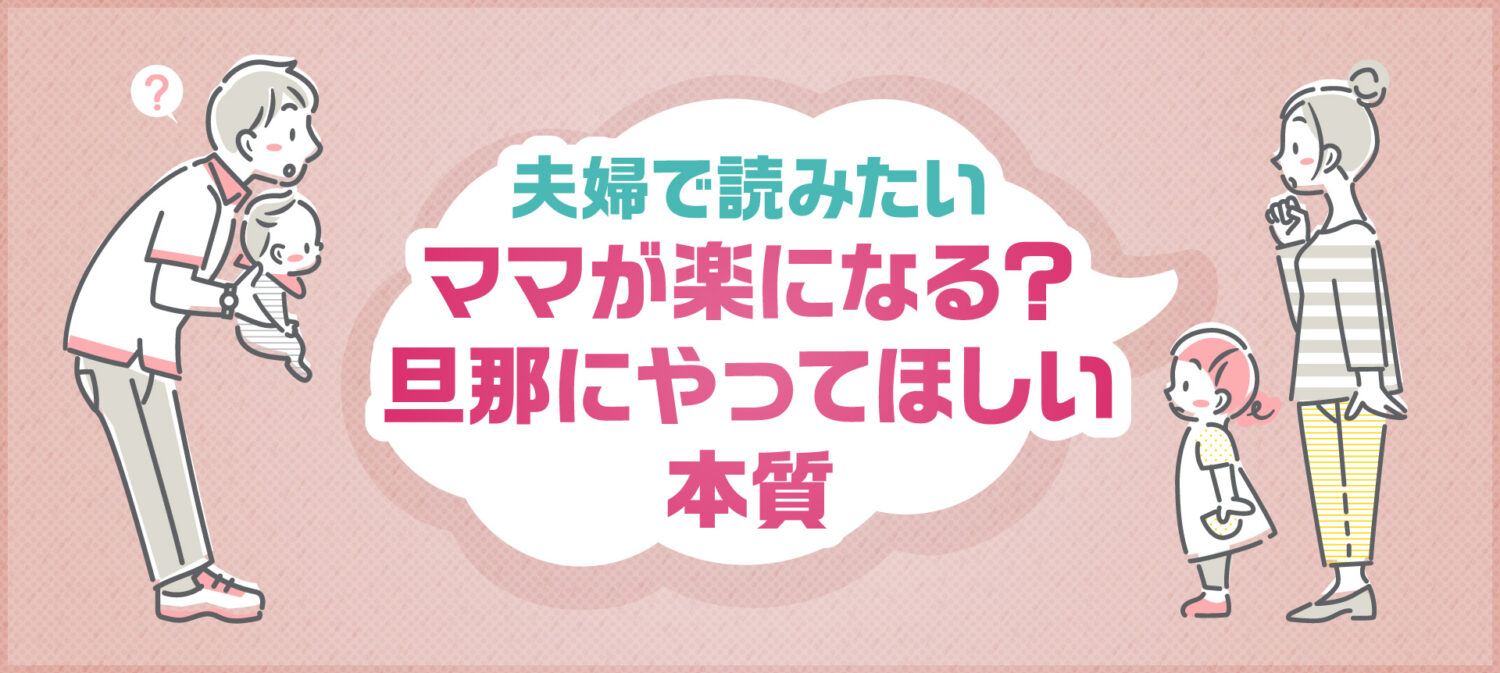うちの家庭は分担しているはずなのに、なんでこんなに私ばかりが疲れるんだろう……。
そんなふうに感じたことはありませんか?家事や育児を半々に分けても、なぜか母親の負担が減らないというケースは少なくありません。実は、家庭がうまく回るために本当に必要なことは、意外とシンプルでした。
この記事は夫婦で読むことを前提に執筆しています。ぜひこの記事から家庭円満のヒントを見つけてみてください。
目次
うまくいっている家庭には理由がある!?負担を感じない家族の共通点
家事や育児の負担は、家庭によって大きく異なります。中には母親の負担が軽く、スムーズに回っている家庭もありますが、こうした家庭にはいくつかの共通点が見られます。どんな違いが負担感に影響するのか、見ていきましょう。
うまくいっている家庭の秘訣とは?

「ありがとう」が自然に飛び交う
感謝を伝えることで、お互いの役割を認め合う雰囲気が生まれています。失敗や不十分でもOK
完璧でなくてもお互いを責めず、サポートする気持ちを大切にしています。自然に役割を補い合っている
必要なことをその場で柔軟に対応し、負担が片方に偏らないよう心がけています。コミュニケーションがしっかり取れている
日常的な会話を通して、互いの気持ちや状況を把握し、理解し合っています。
うまくいっている家庭は、負担をただ分けるのではなく、自然にシェアする姿勢が土台にあることが特徴です。「なんでうちではうまくいかないんだろう?」と感じる方もいるかもしれませんが、うまくいく家庭には、それなりの理由があるようです。
どうしてこんなに偏るの?分担しても母親が疲れてしまう理由
家事や育児を分担しているはずなのに、なぜか母親ばかりが疲れてしまう。そんな経験はありませんか?
一見合理的に思える分担ですが、実はそれが家庭の負担を増やす原因になっているケースが、参考にした文献からも見えてきました。分担が思わぬ不満を生む理由について、詳しく見ていきましょう。
家事や育児を分担していると、逆に不満が溜まりやすいって聞いたことがあるよ。
育児期間中は、ママが家庭を支えてるから、どうしても調整役としての負担が大きくなっちゃうんだにゃん。
分担しても母親の負担が減らないのはなぜ?
分担が「任せきり」を招きやすい
分担することで役割を明確にすることで、自分の担当以外には関わらないという現象がおこりがちになります。結果として家庭全体の管理が母親に集中してしまい、不満が蓄積されることに繋がります。負担が一方に集中しやすい
分担された範囲外で何かが発生したとき、「誰がやるのか?」となると、結果的に母親が対応せざるを得ない状況が生まれがちです。特に、緊急性が低いけれど不可欠な作業は、自然と母親の責任になりやすい傾向があります。柔軟な対応がしにくくなる
役割が決まっていると、予定外のことが起きたときに「それは自分の担当じゃない」と後回しにされがちです。その結果、結局は母親が対応せざるを得なくなり、臨機応変に動く負担が増えてしまうことがあります。第三者の調整役は母親になりがち
祖父母などの第三者の調整役は母親に任されがちで、負担になっている傾向が強い。たとえば、祖父母と意見が合わない場合、対立を避けるために母親が祖父母の意見を尊重するケースが見られます。
分担が進むほどコミュニケーションが減る?
必要な情報共有が抜けがちになる
分担により、互いの役割が固定されると「任せているから大丈夫だろう」と相手に頼りきってしまい、進捗や状況の共有が減りがちです。気づきの差がストレスを生む
役割を分担していると、お互いの負担感に気づきにくく、自然と不満が積み重なることがあります。母親の中には、「もっと分かってほしい」という思いが蓄積しやすくなります。第三者の意見がコミュニケーションを分断する
第三者(たとえば祖父母)との調整役は母親の担当になりやすく、家庭内での意見のすれ違いが進行しやすくなる可能性があります。

分担により互いに責任が固定化されてしまうと、母親が全体の家事・育児の調整役を一手に引き受けるケースが増え、不満が蓄積される傾向にあります。
また、不公平感を埋めるための交渉をしたとしても、その都度抵抗に遭うケースが少なくありません。この過程が母親の疲労を増大させ、結果として役割分担を諦める要因となることが多いようです。
次のセクションでは、分担の根底にある権力構造に焦点を当て、なぜ母親の負担が増えてしまうのかを具体的に探っていきます。
分担では避けられない?分担の根底にみられる権力構造の危険性
家事や育児を分担しているはずなのに、なぜ母親の負担が軽くならないのでしょうか。その背景には、ふだん気づかない「見えない力」が影響していることがあります。
この見えない力は、夫婦がお互い意識していなくても働き、家事や育児の負担が母親に偏りがちになる「権力構造」を生み出します。
見えない権力構造が、ママの負担になっているって知ってた?
え?どんなことにゃ?
実はね、『自分でやったほうが早い』とか『俺の担当じゃない』って気持ちが、ママにいろいろ重くのしかかってるんだよ。
家庭内で見えない力が働く「不可視的権力」と「潜在的権力」
家事や育児の負担が母親に偏ってしまう背景には、目に見えない「不可視的権力」や「潜在的権力」が関係しています。大変さを解決するためにも、問題点を視覚化し、夫婦で共有することが大切です。
「私がやったほうが早い」思考が生む不可視的権力
母親に負担が偏ってしまう背景に、不可視的権力の構造がみられます。
やっぱり自分でやるしかない?
話し合いがうまくいかなかったり、過去の対立が続いたりすると、母親が「いちいち言うより、自分でやるほうが早い」と考えてしまうことが増えてしまいます。周囲の「当たり前」が生むプレッシャー
祖父母や社会から「母親が家庭を支えるべき」という期待が無意識にかかると、母親が家事や育児を引き受けるのが「当然」とされやすくなります。
母親が「自分がやるしかない」と思い込んだり、周囲の無言の期待に応えようとすることで、家事や育児の負担が固定化されていきます。本人が意識しないうちに、見えない形で負担が偏るこの力を「不可視的権力」と呼びます。
「俺の担当じゃない」が生む潜在的権力
母親にばかり負担がかかりやすくなるもう一つの背景には、潜在的権力の構造が働いていることが考えられます。
「俺の担当じゃない」が引き起こす他責思考
役割をはっきり分けたつもりでも、夫が「これは自分の担当じゃない」と考えると、家庭全体の管理が自然と母親に集中してしまいます。「自分の仕事以外には興味がない」という無関心さ
夫が「自分の役割さえこなせばいい」と考え、家庭全体の状況に無関心になると、家庭の流れを管理する負担は母親一人に偏ってしまいます。
分担が進むほど「自分の担当以外は関係ない」という無意識の態度が現れ、結果的に母親が「家庭全体の管理役」を担うことになります。こうした潜在的権力の働きにより、母親は孤立感や負担感を抱えやすくなり、見えない形での負担が増えるのです。
母親が孤独を感じながらも負担を抱え続けてしまうのは、まさにこの潜在的権力が原因です。
「この記事を一緒に見よう!」見えない負担を共有する第一歩
家事や育児の負担が母親に集中しがちな背景には、目に見えない「不可視的権力」や「潜在的権力」が関係しています。ですが、家族が協力し合うためには、まずこの負担を「見える形」にすることが大切です。
たとえば、この記事を夫と一緒に読んでみるのも、その一歩になるかもしれませんし、その目的のために記事を執筆しました。お互いに負担の偏りに気づき、無意識の役割分担が見直せるきっかけとなれば幸いです。
家事や育児をただしくシェアしていくためには、まず現状を二人で知ることが大切です。
不公平感を減らすカギは「シェア育児」にあり
「シェア育児」を取り入れることで、家事や育児の役割分担による不公平感や偏りを減らし、家族全員が協力し合える体制が生まれます。母親と父親が一緒に支え合い、シェアの意識を持って取り組むための方法を確認しましょう。

シェア育児を成功させるためのポイント
シェアは母親が行い、父親が受け持つ意識を持つ
家事や育児は、夫婦共に主体的に行うものですが、特に育児中は母親のほうが細かな変化に気づきやすいのが現実です。つまり、母親が「これをシェアしよう」と意識し、父親がそれを「受け持つ」意識を持つことが、シェア育児を成功させる秘訣です。夫は「受け持つ」という姿勢を大切にする
夫が「自分の役割」として積極的に受け持つ意識を持つことで、家事や育児の負担が共に分かち合えるようになります。もちろん主体的に動くことで、母親の負担も軽減されます。頼まれたら嫌な顔をしない努力を(潜在的権力の抑制)
夫が嫌な顔をすると頼む雰囲気ではなくなります。頼まれたときは、協力する姿勢を見せることで、潜在的権力を抑制することができ、母親が孤立感を抱えにくくなります。母親は夫に過度な期待をしないこと(不可視的権力の抑制)
夫に過度な期待を抱きすぎると、「どうせ自分でやるしかない」という思い込みが働きやすくなります。「完璧でなくてもいい」と考えることで、母親自身が負担を抱え込む「不可視的権力」を和らげることができます。お互いに感謝の気持ちを持ち続ける
小さなことでもお互いに感謝を伝えることで、信頼と協力が深まります。「ありがとう」の気持ちがシェア育児を円滑にし、家族全体の絆を強くします。無理なく、まずは小さなことから始めてみませんか?
シェア育児は、一度に完璧を目指すものではありません。小さなことから少しずつ始めることで、夫婦がお互いの支えを感じながら前に進むことができます。目の前の幸せを一緒に積み重ねていきましょう。
お互いを思いやる気持ちを持つことが大切
家事や育児の役割をきめたとしても、役割に固執せず、その時々で柔軟にシェアできる体制を作ることが重要です。
仕事で忙しい日や体調が悪い日もあります。そうした状況をお互いに理解し合い、「自分も頑張っているけれど、相手も頑張っている」と思いやる気持ちを持つことが、無理のないシェア育児につながります。
役割を柔軟にシェアするための工夫
体調や予定に合わせて役割を交替する
その日の仕事の状況や体調に合わせて柔軟に対応しましょう。どちらか一方に負担が集中することを防ぎ、協力する意識が高まります。休日は夫がワンオペ育児を担当してみる
休日に夫が子どもを一人で見ることで、お母さんが休める時間ができ、夫も子どもの様子をよく知るきっかけになります。こうした体験がシェア育児のスタートになります。定期的に話し合い、状況に応じて協力の仕方を見直す
家事や育児の負担が一方に偏らないよう、夫婦で定期的に話し合い、それぞれの状況や気持ちを確認しながら協力の仕方を調整しましょう。
実は、冒頭で紹介した「うまくいっている家庭」は、こうした柔軟な調整とお互いを思いやる気持ちを大切にしています。
その時々でお互いに協力し合いながら家庭を支えることで、負担が自然にシェアされているのです。シェア育児をスムーズに進めるためにも、まずはこの柔軟さと思いやりの気持ちを土台にしてみませんか?
お互いを思いやり、自然なシェア育児を目指そう
家庭での家事や育児をスムーズに分かち合うには、ただ役割を分担するのではなく、そのときどきで柔軟にシェアする姿勢が大切です。お互いの状況や気持ちを尊重しながら、無理なく協力し合うことで、家族全体が支え合える環境が生まれます。
この記事のポイント
シェア育児がうまくいく家庭の共通点
「ありがとう」が自然に伝えられ、失敗や不足も受け入れる姿勢がある。分担だけでは解消されない母親の負担
固定した分担が逆に母親の負担を増やし、柔軟な対応が必要。不可視的権力と潜在的権力
見えない負担が母親に集中する構造を、夫婦で視覚化し共有する大切さ。シェア育児に向けた工夫
夫が主体的に参加し、定期的な話し合いや休日のワンオペ体験で理解を深める。
柔軟さと思いやりの気持ちを大切に、お互いを支え合うシェア育児に取り組んでみましょう。小さな一歩が、家族全員にとっての大きな安心に繋がります。
この記事を書くにあたり、以下の文献を参考にしました。
参考文献1:J-STAGE 日本心理学会大会発表論文集(父親の育児家事参加と母親の育児不安の検討)参考文献2:J-STAGE 家族社会学研究(家事育児の分担に見る夫と妻の権力経験――育児期の共働き家庭の事例を用いて――)
\この記事をシェアする/