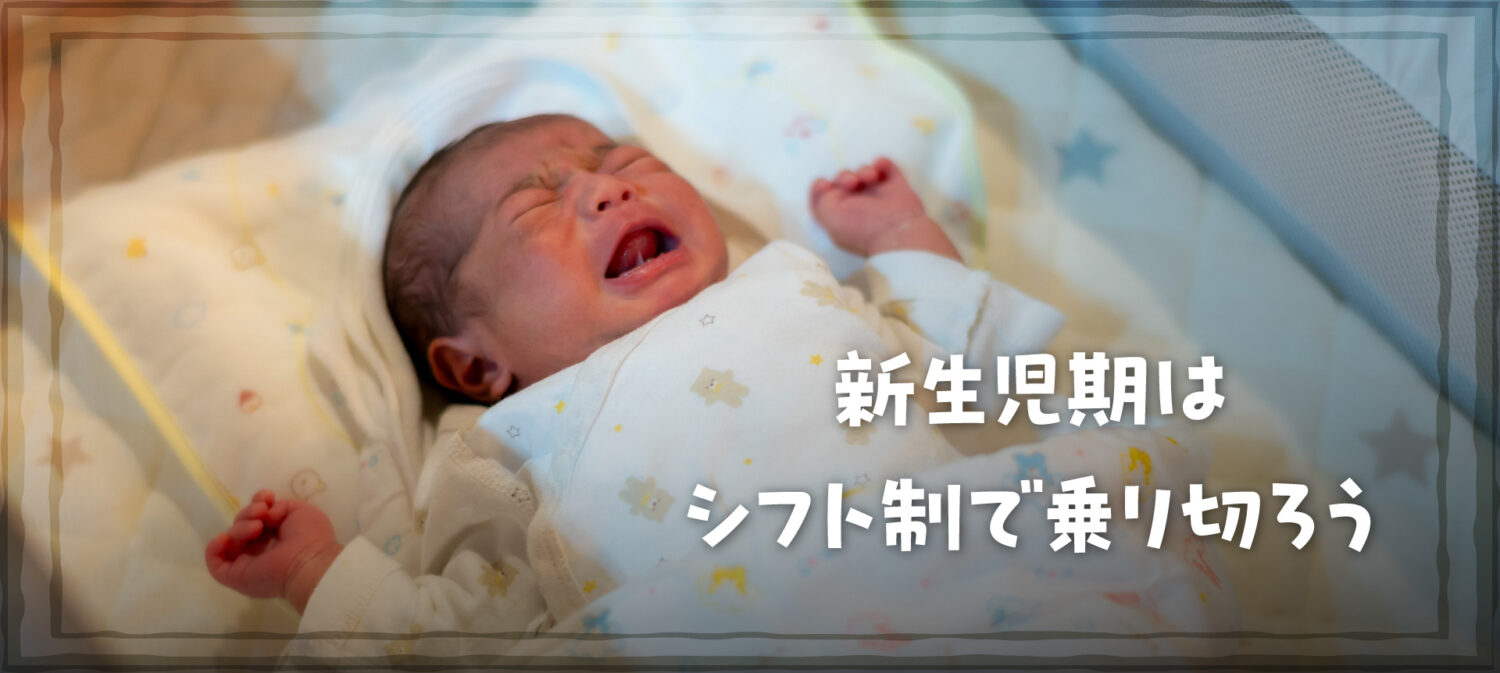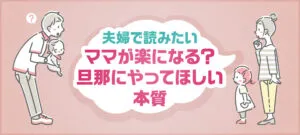これから新生児期を迎える方へ。家事や育児を分担するのではなく、シフト制を取り入れてみませんか?
一見、合理的に見える分担制ですが、実は負担が偏りやすく、夫婦間の喧嘩の原因になることもあります。その点、シフト制なら新生児期の心身の負担を軽減し、育児をスムーズに進める秘訣が存在します。
この記事では、シフト制のメリットと導入のポイントをご紹介します。
目次
育児の分担、なぜうまくいかない?
家事や育児を「分担」するのは一見合理的に思えますが、実際には負担が偏りやすく、不満が溜まりがちです。
特に育児においては、分担制にはいくつかの大きな問題があり、かえって夫婦のストレスや摩擦の原因になることが少なくありません。分担がうまくいかない理由について見ていきましょう。
家事や育児の分担って、やってみると意外と片方に負担が偏りがちなんだよね。
お互いの状況が見えにくくなるからこそ、誤解が生まれて、気持ちのすれ違いが増えちゃうんだよなぁ。
負担の偏りが不満を生む
役割を分担することで、それぞれの役割が明確にはなるものの、実際にはどちらか一方に負担が集中しがちです。育児では予測不能な事態が頻発するため、片方が「自分ばかり大変な思いをしている」と感じやすくなり、不満が蓄積されていきます。
負担が偏りがち
分担を決めても計画通りに進まないことが多く、いつの間にか片方に負担が集中しがちです。育児や家事のバランスが崩れ、特に体力的な疲れが一方に偏ることが増えます。イライラや不満が生まれやすい
どちらかが休息を取っていると、もう一方が「自分ばかり負担している」という不満を感じやすくなります。こうした思いが積み重なり、イライラや不満が募りがちです。不満が蓄積しやすい
負担が集中することで、相手への不満が蓄積され、ストレスとなっていきます。小さな不満でも放置すると大きくなり、夫婦のすれ違いの原因となります。
コミュニケーションが減少する
分担制では、お互いが自分の役割に集中するため、相手の状況や苦労が見えにくくなります。お互いの負担を共有する機会が減り、「自分ばかり頑張っている」という誤解が生じやすく、夫婦間での気持ちのすれ違いや摩擦の原因にもなります。
情報が共有されにくい
それぞれが自分の役割に集中するあまり、相手がどのように過ごしているか、何を感じているかが見えづらくなります。これにより、ちょっとした不満やストレスを共有する機会が減りがちです。気持ちのすれ違いが起きやすい
分担していると、互いの負担や大変さを理解する機会が減ります。そのため、「自分ばかり頑張っている」と感じやすくなり、お互いの気持ちにすれ違いが生まれる原因になります。
お互いの粗が見えやすくなる
分担制では、相手のやり方に自然と目が向きやすくなり、自分とは違う進め方に「こうすればいいのに」といった不満が出がちです。小さなミスや違いが気になり、つい批判的になってしまうことで、夫婦間の摩擦が増幅することもあります。
進め方の違いで不満が生まれやすい
分担制では、相手のやり方が気になりがちです。「こうすればいいのに」といった不満が生まれやすく、相手への不満が積み重なる原因になります。小さな違いにイライラし、摩擦が増幅する
自分と異なるやり方が目につきやすくなり、些細な違いにイライラが募ります。小さな不満が積もり、やがて夫婦間の摩擦を大きくすることもあります。
もっと家事・育児がうまくいく!おすすめ記事まとめ
分担がもたらす落とし穴について詳しく知りたい方へ
妻の負担が偏りがちになる原因については、こちらの記事も参考になります。日常的な見えない家事の負担や、育児における精神的負荷の問題を掘り下げて解説しており、家庭内でのシェア育児を考えるヒントが得られます。
こちらもどうですか?
分担の課題をさらに理解するために
家事や育児の負担がなぜ偏りがちになるのか、また、分担制がかえって負担や不満を増やす原因について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。夫婦が協力しやすい環境を作るためのヒントも紹介しています。
こちらもどうですか?
新生児育児にシフト制が最適な理由
新生児期の育児は昼夜を問わず続くため、夫婦にとって大きな負担となります。この時期には分担やシェアよりも、交代で育児と休息を取り合う「シフト制」が効果的です。
新生児の育児って、昼も夜も関係なく続くから、疲れがたまりやすいんだよね。
それにゃらシフト制が役に立つんだにゃ。
育休があるときは3時間ごとに交代したり、育休がないなら週末にパパが多めに担当するといいにゃん。
たしかにお互い無理なく支え合えるし、良いかもしれないね。
育休の有無に応じた工夫が必要
シフト制は新生児育児に非常に有効ですが、育休の有無に応じて工夫が必要です。
育休中のパパの場合
夜間や日中のシフトを細かく設定し、ミルクをあげるタイミング、つまり3時間ごとに交代することで、お互いに一定の休息時間を確保できます。育休がないパパの場合
週末にパパが積極的にシフトを引き受けたり、夜間の一部を担当する方法がおすすめです。平日の負担を補い、ママの休息時間を確保しましょう。
夫婦の状況に合わせたシフト制の工夫が、無理なく育児を進めるポイントになります。
母乳育児も工夫が必要
母乳育児の場合、授乳はどうしてもママの役割になるため、通常のシフト制にいくつかの工夫を加えると効果的です。

母乳の前後でシフトを分割する
授乳タイミングと授乳前後をシフト分割することで、ママは授乳のみに集中のもオススメです。ママは短い時間でも確実に休息を取ることができます。夜間は混合育児にする工夫
夜間だけはパパがミルクを担当する「混合育児」にするのも一つの方法です。混合育児や完ミなら、パパも育児に積極的に関われる時間が増え、ママがまとまった休息を取れるようになります。搾乳機を導入すれば夜間も安心
母乳育児をしている場合は、搾乳機を導入してみてはいかがでしょうか?母乳を入れるためのパックも売っていますので、小分けにして複数回の保存をすることも可能です。
休息と集中のバランスが取れる
シフト制なら、交代で休む時間と育児に集中する時間を確保できます。育児中のストレスの多くは睡眠不足から生じるため、しっかり休息を取ることで気持ちに余裕が生まれ、穏やかな気持ちで育児に向き合えるようになります。
- 十分な休息を取ることで、体力や気力の消耗を防ぎ、夫婦ともにリフレッシュできる
- 休息と集中を交代でバランスよく取ることで、負担が一方に偏らない
相手の大変さを理解しやすくなる
シフト制を取り入れると、夫婦が同じような作業を経験するため、互いの苦労や大変さが自然と伝わりやすくなります。相手の負担を実感することで、夫婦間のコミュニケーションも増え、協力体制が強まります。
- 共通の体験を通じて、相手の大変さを理解できる
- コミュニケーションが自然に増え、相手の状況への気づきが生まれる
負担と休息を共有できる
シフト制では、交代で「育児の大変さ」を経験すると同時に、同じように「休息」も分かち合えるため、「自分だけがつらい」と感じにくくなります。夫婦が共に負担を理解し、休息を共有することで、ストレスが軽減され、育児をより穏やかに続けられます。
- 負担と休息を公平にシェアできるため、不満が溜まりにくい
- 「自分ばかり」という思いが少なくなり、夫婦で支え合える環境が整う
シフト制をうまく取り入れるために
シフト制を実際に導入するためには、夫婦で無理なく続けられる工夫が重要です。ここでは、シフト制を効果的に取り入れるためのポイントと、スケジュール例を紹介します。
ミルクの時間をベースにシフトを設定
新生児期は3時間ごとの授乳が基本です。このリズムをシフトの基準にすると、自然に交代できるため、夫婦どちらかが極端に疲弊しないバランスが取りやすくなります。夜間もミルクやおむつ替えのタイミングでシフトを交代するようにすると、負担を分散でき、安心して休息が取れます。
シフト制スケジュール例
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 0:00 - 0:30 | ママ(授乳) |
| 0:30 - 3:00 | パパ(授乳後のケア、おむつ替え) |
| 3:00 - 6:00 | パパ(ミルク、おむつ替え) |
| 6:00 - 9:00 | ママ(授乳、おむつ替え) |
| 9:00 - 12:00 | ママ(授乳、おむつ替え) |
| 12:00 - 12:30 | ママ(授乳) |
| 12:30 - 15:00 | パパ(授乳後のケア、おむつ替え) |
| 15:00 - 15:30 | ママ(授乳) |
| 15:30 - 18:00 | パパ(授乳後のケア、おむつ替え) |
| 18:00 - 18:30 | ママ(授乳) |
| 18:30 - 19:00 | パパ&ママ(沐浴、協力して実施) |
| 19:00 - 21:00 | ママ(おむつ替え) |
| 21:00 - 0:00 | ママ(授乳、おむつ替え) |
情報共有を欠かさない
シフトの交代時には、お互いに気づいた点や改善が必要なことを共有する時間を取りましょう。

たとえば、赤ちゃんの様子や気づいた小さな変化も共有することで、育児の流れが途切れにくくなり、よりスムーズな協力体制が生まれます。情報を共有することでお互いの理解が深まり、より効果的にシフト制を続けられます。
- 交代時に共有する時間を作る:赤ちゃんの様子や注意点を伝える
- 気づいた改善点を話し合う:次のシフトに活かし、育児の流れを途切れさせない
柔軟に調整していく
最初から完璧なシフト制を目指す必要はありません。夫婦のリズムや生活状況に合わせて少しずつ調整し、無理のない形を見つけていくことが大切です。シフト制をうまく機能させるポイントは、お互いが納得して続けられる方法を見つけることにあります。
- シフト制は徐々に調整:無理なく続けられるリズムを見つける
- お互いの状況に合わせて柔軟に対応:その時々の変化に合わせて調整
また、急なトラブルが発生することもあります。
たとえば、子どもの体調が悪そうなときや、ウンチ漏れといった予想外のケアが必要な場面では、シフトにこだわらず夫婦で協力して対応しましょう。また、日中に特に忙しい日が続いている場合も、お互いの状況に合わせて臨機応変に交代することで、家庭全体がスムーズに回りやすくなります。
状況に応じてお互いがサポートし合える形で進めることが、成功の鍵です。
夜間のシフト制からシェア育児への移行
新生児期は、夜間も含めた頻繁な授乳が必要ですが、生後2ヶ月を過ぎたあたりから、徐々に授乳間隔をあけることができるようになります。交代のシフト制を少しずつ緩め、柔軟にサポートし合うシェア育児へ移行することで、夫婦双方の負担軽減を進めましょう。
新生児期が終わってくると、少しずつ夜間の授乳も減らせるようになるよね。シフト制からシェア育児に移行すると、もっと育児が楽になるかも。
役割をその場の状況に合わせて柔軟に変えられると、ストレスが少なくなるにゃ。夫婦でお互いを支え合うのが大事じゃ。
うん、互いに「ありがとう」って言い合えると、気持ちもずっと穏やかでいられるよね。
夜間の負担軽減のポイント
生後2〜3ヶ月頃から、夜間の授乳間隔をあけることが可能になり、夜間の負担を軽減することができます。無理なくシフト制を緩め、夜間の負担を少なくしていきましょう。
日中の授乳量をしっかり確保する
日中にしっかり授乳を行うことで、赤ちゃんが夜間に空腹を感じにくくなり、夜間の授乳頻度を徐々に減らせるようになります。赤ちゃんが落ち着いて眠れる環境を整える
夜間に赤ちゃんが長く眠れるように、寝室を暗くして静かな環境を作ると、夜の授乳間隔が延びやすくなります。
シェア育児への移行のメリット
夜間の頻回授乳が減ることで、夫婦ともにまとまった休息を確保でき、育児の負担がさらに軽減されます。シフト制からシェア育児へ移行することで、日中の家事や育児をお互いに協力して進め、ストレスも軽減され、家族全体がより快適に過ごせるようになります。
夜間のストレスが減少し、夫婦の睡眠が安定
夜間の負担が軽くなることで、夫婦ともに精神的な余裕が生まれ、穏やかな気持ちで育児に向き合えるようになります。日中のシェアで育児のバランスが整う
シェア育児に移行することで、日中の育児や家事を効率的に協力して進められる体制が整い、生活リズムが整いやすくなります。夫婦が互いにサポートし合う体制が、育児生活をスムーズに進める基盤となります。
ちなみにシェア育児とは
シェア育児は、お互いの状況や得意分野に合わせて役割を柔軟にシェアし、無理なくサポートし合うことが特徴です。
妻がシェアし、夫が受け持つ
妻が「これをシェアしよう」と意識し、夫がその役割を「受け持つ」姿勢を取ることで、夫婦の協力体制が整います。育児や家事の役割を自然に分かち合い、負担が偏らないように進めます。その場の状況に応じて役割を柔軟に調整
忙しいときや急な用事があるときには、夫婦で臨機応変に役割を交換し、状況に応じてサポートし合います。負担を一方に集中させない工夫が大切です。コミュニケーションを重視する
日々の家事や育児の進捗を互いに共有し、子どもの成長や家庭の状況を把握することで、よりスムーズにサポートし合える体制が生まれます。「褒め上手・頼まれ上手」を目指す
お互いに「ありがとう」と感謝を伝え合い、頼みごともしやすい雰囲気を作ることで、夫婦間で気持ちよく役割をシェアできるようになります。
シェア育児は、役割を固定せず柔軟にサポートし合うことを通じて、夫婦が協力して育児に向き合うスタイルです。
シフト制で新生児期を乗り切って、育児を盤石な体制に!
新生児期の育児では、交代で育児と休息を取り合う「シフト制」を取り入れることが、負担の軽減に効果的です。
また、成長とともに夜間の負担が軽減されたら、シフト制から柔軟な「シェア育児」へと移行することで、さらに家族の協力体制が強まり、家族全員が心地よく育児に取り組めるようになります。
この記事のポイント
新生児期はシフト制が最適
3時間ごとなどに交代で育児と休息をとることで、夫婦ともに無理のない形で育児が可能になります。母乳育児も工夫で柔軟に
夜間のみミルクを使うなど工夫することで、母親もまとまった休息を確保しやすくなります。成長に合わせてシェア育児へ移行
授乳間隔があいてきたら、日中の家事や育児を柔軟にシェアすることで、夫婦の協力体制が整いやすくなります。シェア育児のコツ
日々の変化に合わせてサポートし合い、お互いに感謝やねぎらいの気持ちを伝え、夫婦で協力する体制を築くことが重要です。
シフト制とシェア育児の両方をうまく活用することで、育児生活の負担を無理なく軽減しながら、夫婦の絆や家族全体の幸せを深めていけます。まずは今できる工夫から少しずつ取り入れ、家族にとってベストな育児スタイルを見つけていきましょう。
\この記事をシェアする/